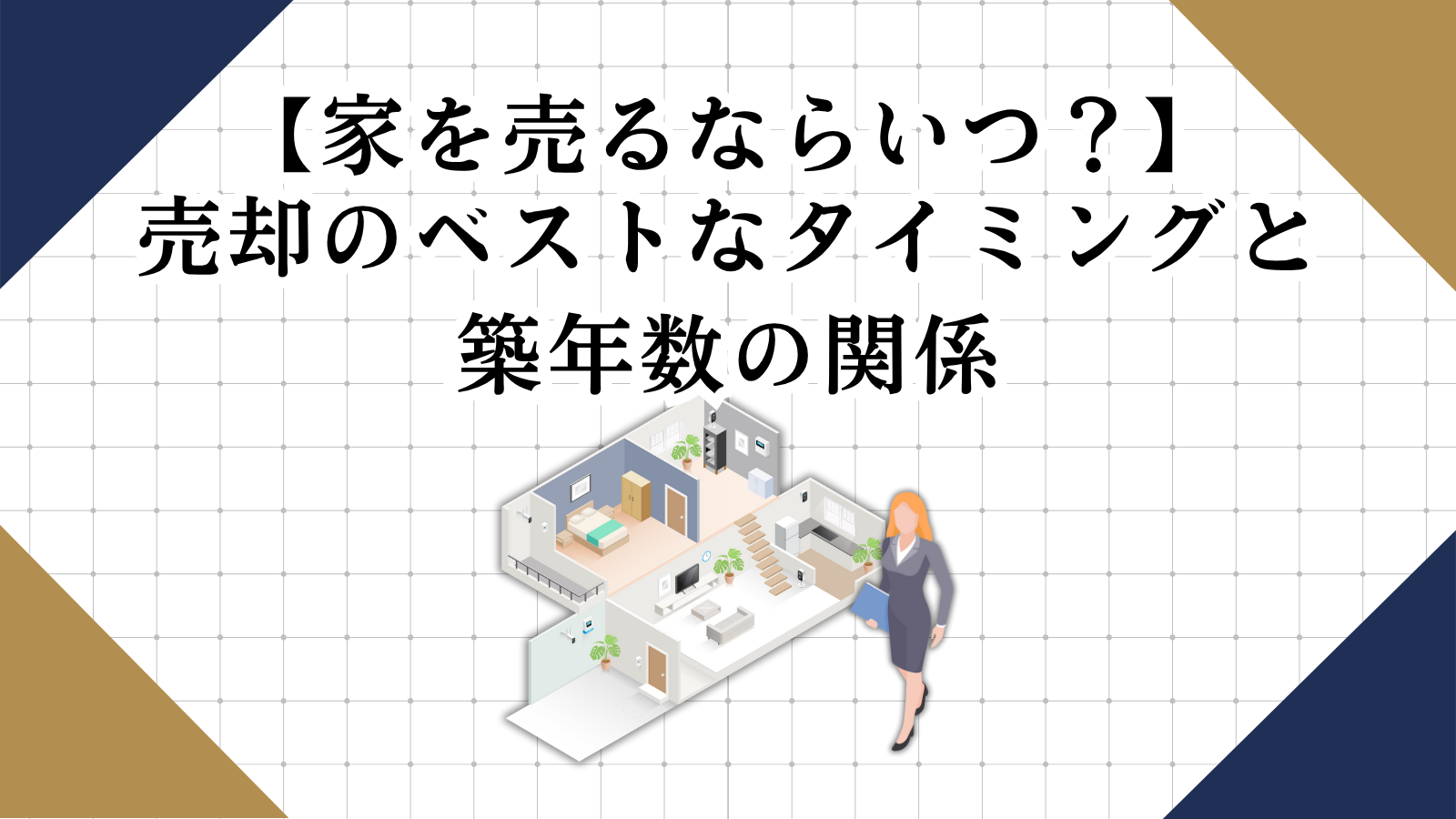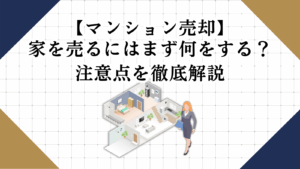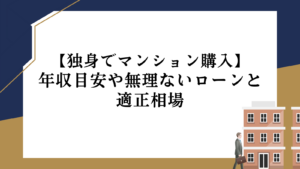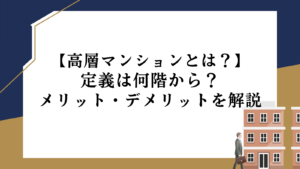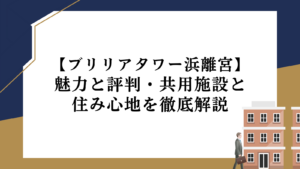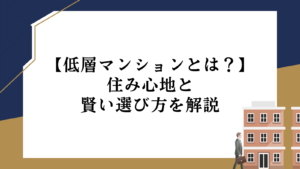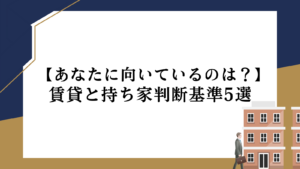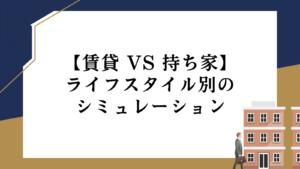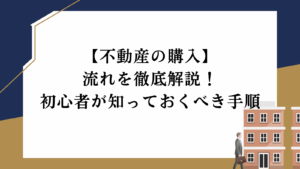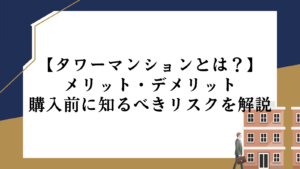「家を売るなら、いつがベスト?」これは売却を考える誰もが悩む点です。築年数が経つにつれ「価値が下がるのでは」と焦る一方、「今が売り時」という情報に迷う方も多いでしょう。
この記事では、売却タイミングを見極めるための「市場・季節」「築年数と価格の関係」「税金(所有期間)」という3つの重要な基準を徹底解説します。
家を売るなら知っておきたい!市場動向と売れやすい季節
家の売却タイミングを考えるとき、まずは「外的要因」、つまり自分ではコントロールできない市場の動向や季節的な需要を知ることが重要です。
これらを把握することで、世の中の「売り時」の波に乗り、より有利な条件で売却を進める戦略が立てられます。
不動産市場の動向:2024年〜2025年は「売り時」の一つと言われる理由
「今は売り時かもしれない」という言葉を耳にする機会が増えていますが、それには明確な理由があります。
- 不動産価格の高止まりと中古需要の増加
- 新築マンションや新築戸建ての価格は、建築資材の高騰や人手不足の影響で上昇を続けています。そのため、多くの買い手が「新築は高すぎる」と判断し、状態の良い中古住宅に目を向けるようになりました。この結果、中古市場の需要が高まり、価格も高止まりしている傾向にあります。
- 歴史的な低金利の継続
- 住宅ローン金利は依然として低い水準で推移しています。買い手にとっては、少ない利息負担で高額な家を購入できる絶好のチャンスです。「低金利のうちに買ってしまいたい」という購買意欲が、市場全体を活発にしています。
- 「売り時を逃したくない」という需要の高まり
- 「価格が高いうちに売りたい」と考える売主と、「金利が低いうちに買いたい」と考える買主、双方の需要がマッチしているのが現在の市場です。今後、金利が上昇局面に転じたり、景気が後退したりすれば、このバランスが崩れる可能性もあります。だからこそ、需要が活発な「今」が売り時の一つとして注目されているのです。
買い手の需要が高まる季節はいつ?(1月~3月・9月~11月)
不動産市場には、服と同じように「シーズン」があります。買い手の活動が活発になるのは、以下の2つの時期です。
- 新生活シーズン(1月~3月)
- 一年で不動産が動く時期です。4月からの就職、転勤、子供の進学・入学に合わせて住まいを探す人が急増します。買い手の需要がピークに達するため、多少強気な価格設定でも売れやすく、高値での売却が見込めます。
- 秋の転勤シーズン(9月~11月)
- 春に次いで需要が高まる時期です。秋の異動や、気候が良く引越し作業がしやすいため、「年内に新居を決めたい」と考える人が活発に動きます。
- 逆に、真夏の8月(お盆休みで家族が揃わない)や、年末の12月下旬(師走の忙しさや新年に向けての準備)は、買い手の動きが鈍くなる傾向にあります。
ベストシーズンに売るための売却活動スケジュール
ここで重要なのは、「一般的に売れやすい時期」に「売りに出ている」状態を作ることです。家の売却は、査定から契約、引き渡しまで通常3ヶ月~6ヶ月程度かかります。
例えば、需要が高まる「3月の引き渡し」を目指すなら、以下のような逆算スケジュールが必要です。
- 前年の11月~12月
- 不動産会社に査定を依頼
- 媒介契約(売却を依頼する契約)を締結
- 1月
- 物件の販売活動スタート(インターネット掲載、内覧対応)
- 1月下旬~2月
- 買主決定、売買契約を締結
- 3月
- 買主のローン審査、残金決済、物件の引き渡し
このように、ベストシーズンを逃さないためには、その時期の3~4ヶ月前から準備を始める必要があります。「そろそろ春だから売ろうか」では、美味しい時期を逃してしまうのです。
戸建て・マンション別の価格下落
家の売却価格を決定づける大きな要因、それは「築年数」です。市場や季節は「売りやすさ」に影響しますが、築年数は「資産価値そのもの」に直結します。
ここでは、多くの方が不安に思う「築年数による価値の下落」について、戸建て・マンション別に詳しく解説します。
【戸建て】築年数と資産価値の関係
「築20年~25年で建物価値がゼロ」は本当か?
この言葉をよく耳にしますが、これは税務上の「法定耐用年数(木造住宅は22年)」に基づく考え方です。あくまで税金の計算上、建物の価値がなくなる目安であり、実際の売買で「価値がゼロ円」になるわけではありません。
しかし、市場の評価として「築20~25年」は大きな節目であることも事実です。多くの金融機関が住宅ローンの審査でこの年数を一つの基準にするため、買い手がローンを組める年数に制限がかかり、結果として売れにくくなる(=価格が下がる)傾向があります。
土地と建物の価格比率
戸建ての売却価格は「土地の価格+建物の価格」で構成されます。築年数が経過すると「建物の価格」は下がりますが、「土地の価格」は景気や立地によって変動します。都心部や駅近など、立地が良い場所であれば、建物が古くなっても土地の価値が価格全体を支えてくれます。
新耐震基準(1981年6月)が査定に与える絶対的な影響
築年数で重要な一線が「1981年(昭和56年)6月1日」です。この日以降に建築確認を受けた建物は「新耐震基準」を満たしており、一定の耐震性が担保されています。
これ以前の「旧耐震基準」の建物は、耐震性に不安があると見なされ、買い手が住宅ローン控除を使えない、ローン審査が厳しくなるなど、売却において大きなハンデとなります。もし旧耐震の家を売るなら、耐震診断や耐震補強工事が重要になってきます。
【マンション】築年数ごとの価格下落率の目安
マンションは戸建てに比べ、資産価値が維持されやすい傾向にあります。これは、価格に占める「土地の権利(敷地権)」の割合が大きく、立地(駅からの距離など)が重視されるためです。
しかし、やはり築年数による下落は避けられません。一般的に、価格が大きく動く「壁」となるタイミングがあります。
- 築5年~10年
- 新築時の価格(新築プレミアム)がなくなり、価格は一旦落ち着きます。下落率は比較的緩やかです。
- 築15年~20年
- 設備(キッチン、浴室など)の古さが目立ち始め、買い手はリフォーム費用を意識します。また、住宅ローン控除の適用条件(築25年以内など)も関わり、下落幅が大きくなる傾向があります。
- 築25年超
- 金融機関によっては住宅ローンの審査が厳しくなり始めます。ただし、この年数になると価格の下落は非常に緩やかになり、立地や管理状態が良ければ価値が下げ止まるケースも多く見られます。
マンションの価値は「立地」と「管理」で決まると言っても過言ではありません。駅近であること、そして管理組合がしっかり機能し、大規模修繕が計画的に行われていることが、築古でも価値を維持する大きなポイントです。
「築浅(10年以内)」が非常に有利な理由
もし売却する家が「築10年以内」であれば、それは非常に大きなアドバンテージです。
- 買い手の印象が良い
- 内装や設備がまだ新しく、「中古」に対する抵抗感が少ないため、内覧時に良い印象を与えやすいです。
- リフォーム費用が不要
- 買い手は購入後にリフォームする費用を考慮しなくて良いため、その分、高い価格でも購入を決断しやすいです。
- 住宅ローン控除の適用
- 買い手は「住宅ローン控除(減税)」を活用できるため、購入のハードルが下がります。
築浅物件は中古市場で需要が非常に高いため、買主と有利な条件で交渉できる可能性が高まります。
家を売るなら税金とライフイベントも考慮すべき
市場の動向(外的要因)や築年数(物件要因)も重要ですが、最終的に「いつ売るか」を決めるのは、売主である「あなた自身の事情」です。
特に「税金」と「ライフイベント」は、売却のタイミングによって手残りが数百万円単位で変わる可能性がある、非常に重要な判断基準です。
所有期間「5年の壁」とは?(長期・短期譲渡所得)
家を売って利益(売却益=譲渡所得)が出た場合、その利益に対して税金(所得税・住民税)がかかります。この税率は、家の「所有期間」によって大きく変わります。
- 短期譲渡所得(所有期間5年以下):税率 39.63%
- 長期譲渡所得(所有期間5年超): 税率 20.315%
税率が約2倍も違うため、売却益が出る場合は「所有期間5年超え」が絶対条件となります。
この「所有期間5年」は、家を売却した年の「1月1日時点」でカウントします。
例えば、2019年9月1日に購入した家を売る場合、5年が経過する2024年9月2日に売っても「短期譲渡所得」になります。
「長期譲渡所得」になるのは、2024年1月1日を過ぎた、2025年1月1日以降に売却した場合です。このタイミングを間違えるだけで、税金が倍になる可能性があるため、確認が必要です。
「3,000万円特別控除」の適用条件
売却するのが「自分が住んでいた家(マイホーム)」である場合、非常に強力な税制優遇が使えます。
それが「居住用財産の3,000万円特別控除」です。
これは、売却益が出たとしても、最高3,000万円までは非課税(税金がかからない)という特例です。ほとんどの場合、この特例を使えば売却益にかかる税金はゼロになります。
ただし、適用には条件があります。
- 自分が住んでいる家であること。
- 住まなくなった日から3年後の年末までに売却すること。
(例:2024年3月に引越した場合、2027年12月31日までに売る必要がある) - 親子間や夫婦間の売買ではないこと。
- 売却した年の前年、前々年に、この特例やマイホームの買換え特例など、他の居住用財産の売却に関する特例を使っていないこと。
特に「住まなくなってから3年以内」という期限は重要です。転勤などで家を空けている場合、この期限を過ぎると特例が使えなくなり、多額の税金が発生する可能性があります。
住宅ローン残債(アンダーローン)の確認は必須
売却の前提条件として、「売却価格で住宅ローンを全額返済できるか」を確認する必要があります。
- アンダーローン: 売却価格 > 住宅ローン残債
(売却してもお金が手元に残る状態。売却に問題ありません) - オーバーローン: 売却価格 < 住宅ローン残債
(売却してもローンが残ってしまう状態)
オーバーローンの場合、売却時に不足分を自己資金(貯金など)で補填しなければ、家を売ることができません(抵当権を抹消できないため)。
「家を売るなら」と考え始めたら、まずはローンがいくら残っているかを確認し、おおよその売却相場と比較することが必須です。
ライフイベント別の売り時判断
結局のところ、売却の動機でありタイミングとなるのは、個人のライフイベントです。
- 住み替え
- 子供の進学(学区の変更)、家族が増えた(家が狭い)、子供が独立した(家が広すぎる)など。
- 転勤
- 急な辞令により、マイホームを手放す必要がある場合。3,000万円控除の期限(住まなくなってから3年)に注意が必要です。
- 相続
- 実家を相続したが誰も住まない場合。維持費(固定資産税)がかかるため早めの売却が推奨されます。相続した空き家を売る場合の特例(相続空き家の3,000万円特別控除)にも期限があります。
- 離婚
- 財産分与のために売却し、現金を分割する場合。
市場が良くても、ライフイベントのタイミングと合わなければ最適な売却とは言えません。ご自身の人生設計に合わせて判断することが重要です。
家を売るなら「今の価値」の把握から!最適なタイミングを知る方法
ここまで「市場」「築年数」「税金・ライフイベント」という3つの基準と、「待つリスク」を解説してきました。
では、最適なタイミングを判断するために、今すぐ何をすべきでしょうか。
答えはシンプルで、「あなたの家の“今の価値”を正確に知ること」です。
なぜ「査定」がタイミング判断の第一歩なのか
「家を売るなら」と考え始めた段階で、まだ「いくらで売れるか」を具体的に知らない方がほとんどです。
- 今の相場で売れば、ローンを完済できるのか?(オーバーローンではないか)
- 売却益は出そうか?(税金対策は必要か、5年の壁はクリアしているか)
- 売却で得た資金で、次の住み替え計画は成り立つか?
これらはすべて、「今いくらで売れるか(査定額)」という正確な現在地がわからなければ、判断も計画もできません。
市場がいくら良くても、あなたの家の価値がローン残債を下回っていれば、売るに売れない(=まだ売り時ではない)かもしれません。
「査定」は、売却タイミングを判断するための、重要で具体的な第一歩なのです。
まとめ
「家を売るならいつ?」という問いに対する答えは、「すべての人に共通するベストタイミング」は存在しない、ということです。
一般的に最適な売り時は、
- 市場・季節
- 中古需要が高く、買い手が活発な時期
- 築年数・家の状態
- 資産価値が大きく下落する前
- 税金・ライフイベント
- 税制優遇が使え、ご自身の人生設計に合う時期
これら3つの基準が、ご自身の状況にとって良い形で重なった時です。
市場が良く、築年数も浅くても、所有期間が5年未満で税金が高くなるなら待つべきかもしれません。逆に、市場が停滞気味でも、転勤で3,000万円控除の期限が迫っているなら「今」が売り時です。
タイミングを悩んでいる間にも、家の価値は下がり、維持費はかかり続けます。
まずは、あなたの家が「今いくらで売れるのか」という現実の価値を知ることから始めましょう。それが、最適な売却タイミングを見極めるための、確実な第一歩となります。