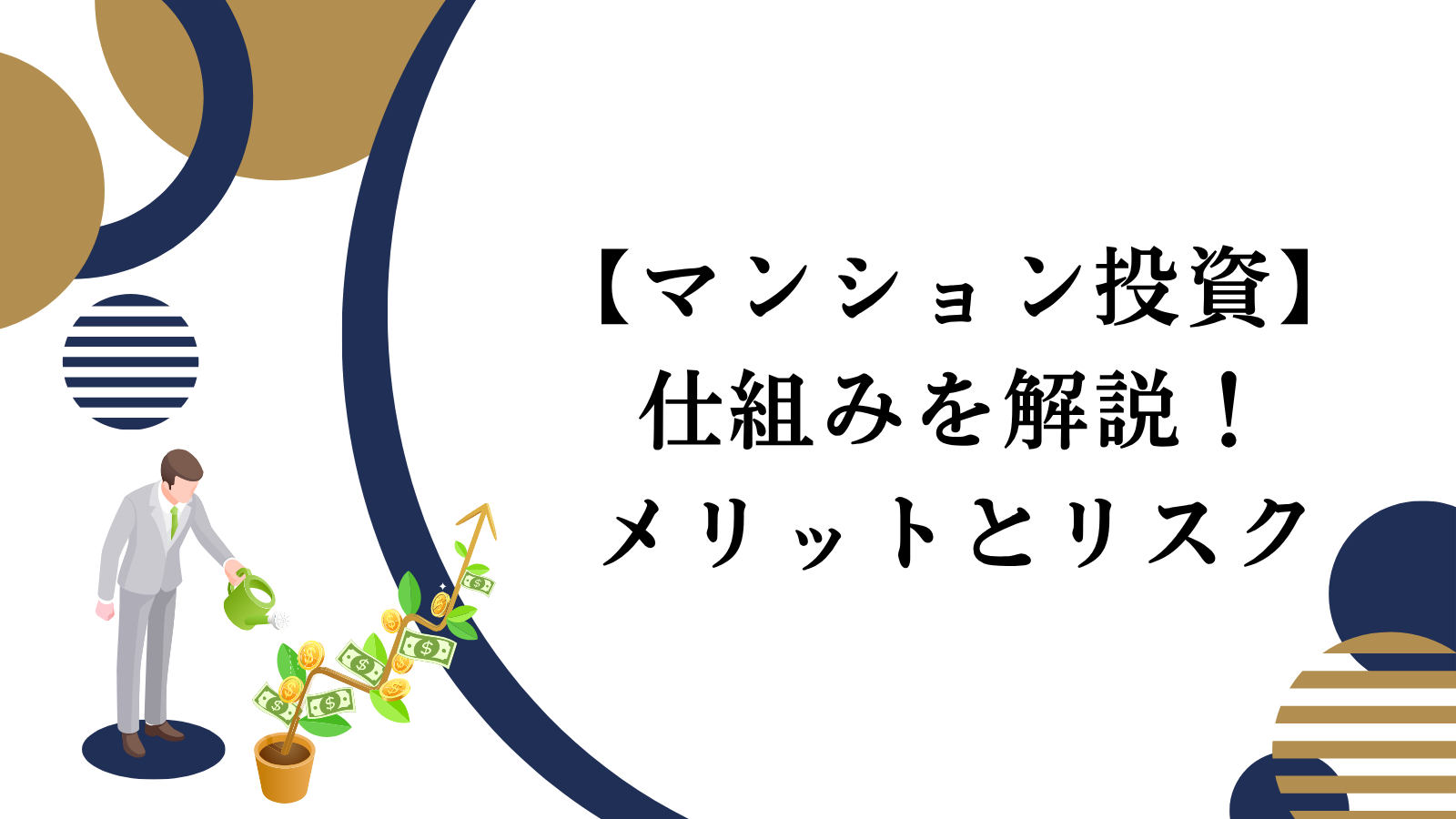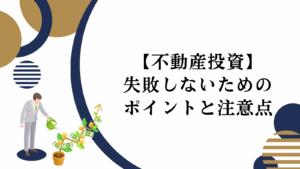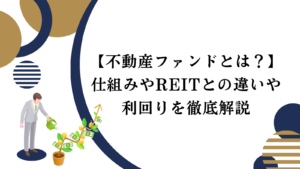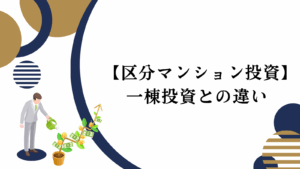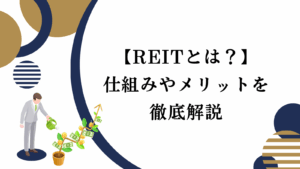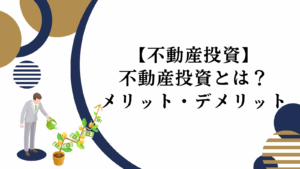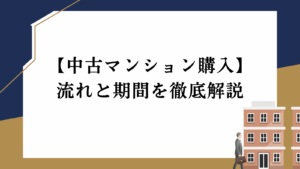将来の資産形成や年金対策として「マンション投資」に興味を持っていませんか?「節税になる」「生命保険代わりになる」といったメリットを聞く一方で、「儲からない」「失敗した」という不安な声もあり、実態がよく分からない方も多いでしょう。
この記事では、マンション投資で収益が生まれる基本的な仕組みなど、知っておくべきリスクを解説します。
マンション投資とは?基本的な仕組みを分かりやすく解説
マンション投資は、分譲マンションの一室、あるいは一棟まるごとを購入し、それを第三者に「賃貸」することで家賃収入を得る投資手法です。まずは、なぜ利益が生まれるのか、その基本的な仕組みを見ていきましょう。
利益を生む2つの仕組み「インカムゲイン」と「キャピタルゲイン」
マンション投資の利益には、大きく分けて2種類あります。
- インカムゲイン(家賃収入)
購入したマンションを入居者に貸し出すことで得られる、毎月の「家賃収入」です。マンション投資におけるメインの収益源であり、長期的に安定した収入が期待できるのが特徴です。ここからローン返済や管理費、修繕積立金などを支払った残りが、オーナー(大家)の利益となります。 - キャピタルゲイン(売却益)
購入した時よりも高い価格でマンションを売却することで得られる「売却益」です。不動産市況の上昇や、再開発によるエリア価値の向上などで利益が期待できますが、常に値上がりするとは限りません。基本的にはインカムゲインを目的とし、キャピタルゲインは「出口戦略」として考えるのが一般的です。
なぜローンを組んでも利益が出る?「レバレッジ効果」とは
「数千万円もするマンションを買うなんて無理だ」と思うかもしれません。しかし、マンション投資の大きな特徴が、金融機関からの「ローン(投資用ローン)」を活用できる点です。
例えば、自己資金300万円で3,000万円の物件を購入した場合、自己資金の10倍の資産を運用していることになります。このように、少ない自己資金で大きな投資効果を狙うことを「レバレッジ効果(てこの原理)」と呼びます。
毎月のローン返済は、入居者が支払う家賃収入から充当できるため、家賃収入を返済に充てることで、自己資金以上の資産を運用できる可能性があります。これが、マンション投資がサラリーマンや公務員にも選ばれる理由の一つです。
アパート一棟投資や戸建て投資との違いは?
同じ不動産投資でも、アパート一棟投資や戸建て投資とは異なる点があります。
- マンション投資(区分所有)
マンション一棟の中の「一室」を購入・所有すること(区分所有)が一般的です。一棟投資に比べて投資額が少なく、初心者でも始めやすいのが特徴です。ただし、共用部分(エントランスや廊下など)の管理は管理組合に委ねるため、自由なリフォームができないなどの制約があります。 - アパート・マンション一棟投資
建物全体を所有します。投資額は高額になりますが、全室からの家賃収入が期待でき、土地も資産として残ります。管理や修繕もすべて自分の裁量で行えますが、その分リスクも大きくなります。 - 戸建て投資
一戸建てを購入して貸し出します。ファミリー層など長期入居が期待できますが、マンションに比べて立地が郊外になるケースも多く、流動性(売りやすさ)が低い場合があります。
マンション投資で得られる5つのメリット
マンション投資が多くの人に選ばれるには、家賃収入以外にも魅力的なメリットがあるからです。ここでは代表的な5つのメリットを解説します。
①毎月安定した家賃収入(インカムゲイン)が期待できる
大きなメリットは、入居者がいる場合、家賃収入が継続的に得られることです。株式投資の値動きのように日々変動するものではなく、家賃相場は株式などの金融商品と比較して景気変動の影響を受けにくい傾向があると言われています。
もちろん空室になるリスクはありますが、立地や物件の条件さえ間違えなければ、適切な物件選定とリスク管理を行うことで、長期的な収益が期待できる投資手法の一つです。
②節税効果が期待できる(減価償却・損益通算)
「マンション投資は節税になる」と聞いたことがあるかもしれません。これは、不動産所得の計算方法に秘密があります。
不動産所得は「家賃収入 - 必要経費」で計算されますが、この経費にはローン金利や管理費のほか、「減価償却費」が含まれます。
減価償却費とは?
建物の購入費用を、法的に定められた耐用年数(例:鉄筋コンクリート造は47年)にわたって分割し、毎年少しずつ経費として計上するものです。実際にお金が出ていかない(キャッシュアウトしない)経費である点がポイントです。
この減価償却費などにより、帳簿上(確定申告上)の不動産所得が赤字になることがあります。給与所得があるサラリーマンの場合、この赤字を給与所得から差し引くこと(=損益通算)ができます。税法上の要件を満たす場合、給与所得と不動産所得の損益通算により、課税所得額が減少する可能性があり、その結果、納めた所得税などが還付される場合があります。
※節税効果については、個人の状況や税制改正によって異なるため、税理士にご相談ください
③万が一の際の保障になる
投資用ローンを組む際、ほとんどの場合「団体信用生命保険(団信)」への加入が義務付けられます。
これは、ローンの契約者(オーナー)が死亡または高度障害状態になった場合に、保険金で残りのローンが全額弁済される仕組みです。
万が一のことがあっても、家族には借金のない収益マンションが残ります。そこから得られる家賃収入は、そのまま家族の生活費や年金代わりになります。これは、一般的な生命保険と同様に、残された家族の経済的なリスクを軽減する効果の一つです。
④インフレ対策としての資産価値
インフレとは、物価が上昇し、相対的に現金(円)の価値が下がることです。例えば、今まで100円で買えたものが120円になる状態です。銀行に100万円を預けていても、その価値は実質的に目減りしてしまいます。
一方、マンション投資のような「実物資産」は、インフレに強いとされています。物価が上昇する局面では、不動産価格や家賃も上昇する傾向があるため、現金の価値が下がっても資産価値を保全しやすいのです。
⑤将来の年金対策・老後の備えになる
公的年金だけでは老後の生活が不安、という方も多いでしょう。マンション投資は、私的年金づくりの手段としても有効です。
現役時代にローンを組み、家賃収入で返済を進めていきます。定年を迎える頃にローンを完済できれば、管理費などを除いた家賃収入のほとんどが手元に残るようになります。毎月安定したキャッシュフローを生み出す資産は、老後の生活を支える大きな柱となります。
知っておくべき6大リスク
メリットの多いマンション投資ですが、当然ながらリスクも存在します。「儲からない」「失敗した」という事態を避けるため、事前にリスクを理解しておくことが重要です。
①空室リスク
マンション投資における大きなリスクは、入居者が決まらず「空室」になることです。空室期間中は家賃収入がゼロになる一方で、ローン返済や管理費・修繕積立金の支払いは待ってくれません。この状態が続くと、自己資金を持ち出すことになり、収支は赤字になります。
②家賃下落リスク
建物は築年数の経過とともに老朽化するため、新築時に比べて家賃は下落していくのが一般的です。購入時の家賃が将来も続くと想定していると、収支計画が狂ってしまいます。
③金利上昇リスク
投資用ローンの多くは「変動金利」で組まれます。変動金利は当初の金利が低いメリットがありますが、将来、市場金利が上昇すると、それに伴って返済額が増加するリスクがあります。
④老朽化・修繕リスク
マンションは経年劣化するため、定期的な修繕が必要です。特に10年~15年に一度行われる「大規模修繕」には多額の費用がかかります。また、室内の設備(エアコン、給湯器など)が故障すれば、その交換費用もオーナー負担となります。
⑤災害リスク(地震・火災など)
地震、台風、火災などで建物が損壊・焼失するリスクです。被害を受ければ、修繕費用がかかるだけでなく、入居者が住めなくなり家賃収入も途絶えてしまいます。
⑥流動性リスク(売りたい時に売れない)
マンション投資は実物資産であるため、株式のように「売りたい」と思った瞬間に現金化できるわけではありません。買い手が見つからなければ売却できず、これを「流動性リスク」と呼びます。
まとめ
マンション投資は、基本的な仕組みとメリット、そして必ず伴うリスクを正しく理解することから始まります。
「節税になる」「儲かる」といったメリットだけを鵜呑みにするのではなく、「空室」や「金利上昇」などのリスクにどう備えるかが、長期的な成功の鍵を握っています。
この記事で解説したポイントを押さえ、まずは信頼できる不動産会社に相談したり、セミナーに参加したりして、自分に合った投資手法なのかをじっくり検討してみてください。リスクを管理し、長期的な視点に立てば、マンション投資はあなたの将来を支える資産となる可能性を秘めています。