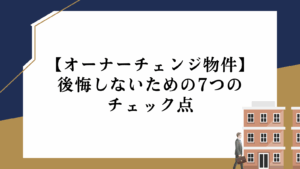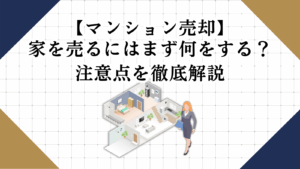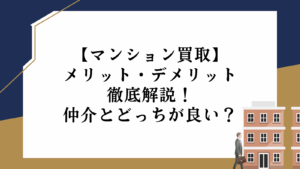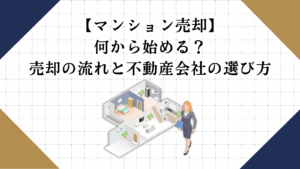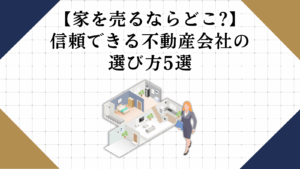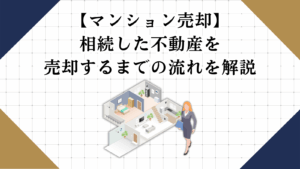不動産を売却した際、「確定申告が必要なの?」「どうすればいいの?」と頭を悩ませる方は少なくありません。
特に初めての売却では、その複雑さに戸惑う方もいるでしょう。
この記事では、不動産売却後の確定申告について、基本的な知識から具体的な手続き、注意点、
さらには活用できる特例制度まで、ステップごとにわかりやすく解説します。
この記事を読めば、あなたが不動産売却後の確定申告をスムーズに進められるよう、全体像を理解できるはずです。
不動産売却における確定申告の基本を理解しよう
不動産を売却した際には、多くの場合、確定申告という手続きが必要になります。
まずは、確定申告の基本的な考え方や、なぜ不動産売却で確定申告が求められるのかについて理解を深めましょう。
そもそも確定申告とは?
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得たすべての所得と、
それに対してかかる所得税や復興特別所得税の額を計算し、税務署に申告して納税する一連の手続きのことを指します。
会社員であれば、通常は会社が年末調整という形で所得税の精算を行ってくれるため、
個人で確定申告をする機会は少ないでしょう。しかし、給与所得以外に一定額以上の所得があった場合や、
特定の控除を受けたい場合などには、個人での確定申告が必要となります。
不動産の売却によって利益が出た場合も、この確定申告が必要となる代表的なケースの一つです。
ただし、以下のようなケースでは確定申告が不要となることもあります。
不動産を売却したからといって、必ずしもすべてのケースで確定申告が必要になるわけではありません。
いくつかの特定の状況下では、確定申告が不要となる場合があります。
例えば、譲渡所得の計算結果がマイナスになった場合、つまり売却によって損失が出た場合で、
かつ他の所得との損益通算や繰越控除といった特例制度を利用しないのであれば、確定申告は原則として不要です。
また、マイホームを売却した際に利用できる「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」など、
特定の特例を適用した結果、課税される譲渡所得が0円以下になる場合も、所得税の納税は発生しません。
しかし重要な点として、これらの特例の適用を受けるためには、
確定申告の手続き自体は必要となる場合がほとんどです。
つまり、税金を納める必要がなくても、特例を使いたいという意思表示として申告はしなければならないのです。
ご自身の状況が確定申告が必要なケースに該当するのか、
あるいは不要なケースに該当するのかを正確に判断することが大切です。
不明な場合は、税務署や税理士に相談することをお勧めします。
なぜ不動産売却で確定申告が必要になるのか?(譲渡所得について)
不動産を売却して得た利益のことを、税法上「譲渡所得」といいます。
この譲渡所得は、給与所得や事業所得など他の所得とは分けて税額が計算される「分離課税」の対象となるため、
会社員の方であっても個人で確定申告を行う必要があります。
譲渡所得は、以下の計算式で算出されます。
譲渡所得=売却価格−(取得費+譲渡費用)
ここでいう「売却価格」とは、不動産を売って買主から実際に受け取った金額のことです。
「取得費」とは、売却した不動産の購入代金や、
購入時に支払った仲介手数料、登録免許税、不動産取得税、改良費などが含まれます。
建物の場合は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた金額となります。 「譲渡費用」とは、
不動産を売却するために直接かかった費用のことを指し、
具体的には売却時の仲介手数料、印紙税、測量費、売却のために建物を解体した場合の解体費用などが該当します。
この計算式で算出された譲渡所得がプラスになる場合、つまり利益が出た場合には、
その利益に対して所得税と住民税が課税されるため、確定申告と納税の手続きが必要になります。
【ステップ別】不動産売却後の確定申告の手順
不動産売却後の確定申告は、いくつかのステップに分かれています。
初めての方でも戸惑わないように、各ステップで具体的に何をすればよいのか、
そのやり方を詳しく解説していきます。
ステップ1:必要書類を準備する ~確定申告のやり方の第一歩~
確定申告の手続きを進める上で、最初に取り組むべき最も重要なことは、
必要となる書類を漏れなく収集することです。書類が不足していると、正確な申告ができなかったり、
受けられるはずの特例が適用できなかったりする可能性がありますので、計画的に早めに準備を始めましょう。
- 確定申告書(所得税及び復興特別所得税申告書、申告書第三表(分離課税用)など)
税務署で入手するか、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。 - 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】
譲渡所得の計算過程を記載する書類で、確定申告書に添付して提出します。
これも税務署や国税庁のウェブサイトで入手可能です。 - 売却した不動産の売買契約書のコピー(売却時・購入時双方)
売却価格や購入価格を確認するために必要です。購入時の契約書が見当たらない場合は、
他の書類で代用できるか確認が必要です。 - 仲介手数料や印紙税などの領収書(譲渡費用がわかるもの)
売却にかかった費用を証明するために必要です。これらをまとめて保管しておきましょう。 - 登記事項証明書
売却した不動産の所在地や面積、所有者情報などを確認するために、法務局で取得します。 - 本人確認書類
マイナンバーカードのコピー(両面)または、マイナンバー通知カードのコピーもしくはマイナンバーが記載された住民票の写しと、運転免許証やパスポートなどの身元確認書類のコピーが必要です。 - 源泉徴収票(給与所得など他の所得がある場合)
給与所得など、不動産売却以外の所得がある場合に必要です。勤務先から発行されます。 - その他、特例の適用を受けるために必要な書類
例えば、居住用財産の3,000万円特別控除を受ける場合には、売却した不動産に居住していたことを証明するための住民票の除票の写しや戸籍の附票の写しなどが必要になることがあります。
適用する特例によって必要書類が異なりますので、事前に確認が必要です。
これらの書類は、税務署や市区町村役場、法務局といった公的機関で取得するものや、
不動産会社との契約時に受け取るもの、ご自身で保管しているものなど多岐にわたります。
リストを作成し、一つずつチェックしながら準備を進めるとよいでしょう。
ステップ2:譲渡所得を計算する ~正確な確定申告のために~
ステップ1で必要な書類が揃ったら、次に行うのは譲渡所得の計算です。
この計算が確定申告における税額計算の基礎となるため、非常に重要なステップとなります。
改めて譲渡所得の計算式を確認しましょう。
譲渡所得=売却価格−(取得費+譲渡費用)
それぞれの項目について、収集した書類を基に正確な金額を把握していきます。
- 売却価格
これは、不動産を売却して買主から実際に受け取った総額です。
売却時に締結した不動産売買契約書に記載されている売買代金を確認します。 - 取得費
売却した不動産を購入した際にかかった費用全般を指します。主なものとしては、
不動産の購入代金そのものの他に、購入時に不動産会社に支払った仲介手数料、
登記の際にかかった登録免許税や司法書士への報酬、不動産取得税、印紙税、測量費、整地費、
建物の建築代金などが含まれます。
建物の場合、購入代金や建築代金から所有期間に応じた減価償却費相当額を差し引く必要があります。
購入時の売買契約書や領収書、請求書などで金額を確認します。
もし、購入時の売買契約書を紛失してしまったなどで実際の取得費が不明な場合は、
売却価格の5%相当額を「概算取得費」として計上することが認められています。
ただし、実際の取得費が5%より大きいことが証明できるのであれば、
そちらを計上した方が有利になる場合があります。 - 譲渡費用
不動産を売却するために直接要した費用です。
具体的には、売却時に不動産会社に支払った仲介手数料、売買契約書に貼付した印紙税、
売却に際して測量が必要だった場合の測量費、建物を解体して土地として売却した場合の解体費用とその損失額、借家人に立ち退いてもらうために支払った立退料などが該当します。売却時の領収書や契約書などで確認します。
これらの金額を正確に計算し、上記の計算式に当てはめて譲渡所得を算出します。
この計算結果がプラスであれば利益が出ていることになり、原則として課税対象となります。
マイナスであれば損失が出ていることになります。損失が出た場合は、確定申告が不要なケースもありますが、
特例の適用を受けるためには申告が必要です。
ステップ3:確定申告書を作成する ~具体的な確定申告のやり方~
譲渡所得の金額が確定したら、いよいよ確定申告書の作成に取り掛かります。
確定申告書を作成するやり方には、いくつかの方法がありますので、ご自身に合ったものを選びましょう。
主な作成方法は以下の通りです。
税務署の窓口で確定申告書(所得税及び復興特別所得税申告書、分離課税用の申告書第三表など)や
譲渡所得の内訳書の用紙を入手し、必要事項を直接手書きで記入していく方法です。
国税庁のウェブサイトから様式をダウンロードして印刷することも可能です。
計算は自分で行う必要があるため、計算ミスや記入漏れがないように細心の注意を払う必要があります。
書き損じた場合は訂正印が必要になるなど、手間がかかる側面もあります。
国税庁の公式ウェブサイト内に設けられている「確定申告書等作成コーナー」を利用する方法です。
画面に表示される案内に従って、収入金額や必要経費などを入力していくと、税額などが自動的に計算され、確定申告書や譲渡所得の内訳書などのPDFファイルを作成できます。
作成したPDFファイルを印刷して税務署に提出することもできますし、
後述するe-Taxを利用して電子申告することも可能です。
計算ミスを防ぎやすく、初めての方でも比較的スムーズに作成できるため、おすすめの方法です。
市販されている会計ソフトや、クラウド型の会計サービスを利用して確定申告書を作成する方法もあります。これらのソフトやサービスは、日々の取引を入力することで自動的に仕訳が行われたり、
不動産売却のような特殊な取引にも対応していたりする場合があります。
サポート機能が充実している製品もあり、税制改正にも対応していることが多いです。
ただし、ソフトの購入費用やサービス利用料がかかる場合があります。
特に不動産売却の確定申告は、譲渡所得の計算や特例の適用など、やや複雑な要素が含まれることがあります。
そのため、計算を自動で行ってくれる「確定申告書等作成コーナー」や会計ソフトの利用は、
手間を軽減し、誤りを防ぐ上で非常に有効な手段と言えるでしょう。
自身のITスキルや予算、かけられる時間などを考慮し、最適な作成方法を選択してください。
ステップ4:確定申告書を提出する ~選べる提出方法~
丁寧に作成した確定申告書は、定められた期間内に所轄の税務署へ提出する必要があります。
申告期間は、原則として所得があった年の翌年の2月16日から3月15日までです。
この期限を過ぎないように注意しましょう。
確定申告書の提出やり方には、主に以下の3つの方法があります。
- 税務署の窓口に持参する
ご自身の住所地を管轄する税務署の窓口へ直接、作成した確定申告書と必要書類を持参して提出する方法です。
税務署の開庁時間内に提出する必要がありますが、
確定申告期間中は日曜日などに休日開庁日が設けられることもあります。
また、税務署に設置されている時間外収受箱へ投函することも可能です。
この場合、投函した日が提出日として扱われます。窓口で提出する際には、
内容について簡単な質問を受ける場合や、その場で受付印を押してもらえるといったメリットがあります。 - 郵送で提出する
作成した確定申告書と添付書類一式を封筒に入れ、管轄の税務署宛に郵送する方法です。
郵送の場合は、通信日付印(消印)の日付が提出日として認められます。
そのため、期限最終日の消印があるものであれば、期限内提出として扱われます。
ただし、普通郵便ではなく、簡易書留や特定記録郵便など、
送達の記録が残る方法で送付することが推奨されます。
これは、万が一の郵便事故に備えるためです。必ず簡易書留や特定記録郵便など、
送達の記録が残る方法で送付することをおすすめします。 - e-Tax(電子申告)で提出する
国税電子申告・納税システムであるe-Taxを利用して、インターネット経由で申告データを送信する方法です。
e-Taxを利用するためには、事前に利用開始の手続きを行い、マイナンバーカードと
ICカードリーダライタ(またはマイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォン)が必要となります。
e-Taxのメリットは、24時間いつでも自宅やオフィスから提出が可能であること、
医療費の領収書や源泉徴収票などの一部添付書類の提出を省略できる場合があること、そして還付申告の場合、
書面提出よりも還付金の処理がスピーディーに行われる傾向があることなどが挙げられます。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告データは、そのままe-Taxで送信することが可能です。
どの提出方法を選ぶかは、ご自身の利便性や状況に応じて判断してください。
期限間際は税務署の窓口が非常に混雑することが予想されるため、郵送やe-Taxを利用するか、
早めに窓口へ持参することをおすすめします。
ステップ5:納税または還付を受ける ~確定申告の最終ステップ~
確定申告書を提出し、申告内容に基づいて所得税額が確定したら、次に行うのは納税または還付の手続きです。
これが確定申告の一連の流れの最終ステップとなります。
納税が必要なケース
譲渡所得があり、計算の結果、納付すべき所得税額が発生した場合は、
定められた期限までに税金を納める必要があります。
納付期限も、原則として確定申告の提出期限と同じく、所得があった年の翌年の3月15日です。
- 振替納税
事前に税務署に依頼書を提出しておくことで、
指定した預貯金口座から自動的に引き落としで納付する方法です。
引き落とし日は申告期限よりも約1ヶ月後になるため、資金繰りに余裕が持てます。 - クレジットカード納付
国税クレジットカードお支払サイトを通じて、クレジットカードで納付する方法です。
納付税額に応じた決済手数料がかかりますが、ポイントが付与される場合もあります。
24時間いつでも利用可能です。 - コンビニ納付
税務署から発行されるバーコード付きの納付書(またはQRコード)を利用して、
コンビニエンスストアのレジで納付する方法です。通常は30万円以下ですが、
利用するコンビニエンスストアや納付方法によって上限額が異なる場合があります。 - 金融機関や税務署の窓口での納付
金融機関(銀行や郵便局など)や所轄税務署の窓口で、現金に納付書を添えて納付する方法です。
ご自身にとって都合の良い方法を選んで、期限までに確実に納税を済ませましょう。
還付を受ける場合
一方で、例えば不動産売却で損失が出たために他の所得と損益通算した結果、源泉徴収などで既に納めている税金が多すぎた場合や、特例を適用した結果、納め過ぎた税金が戻ってくることがあります。これを還付といいます。
還付金は、確定申告書に記載したご自身の預貯金口座に振り込まれます。
e-Taxで申告した場合、通常、書面で申告した場合よりも還付金の処理が早く進む傾向にあり、
おおむね2週間から3週間程度で振り込まれることが多いようです。
書面提出の場合は、1ヶ月から1ヶ月半程度かかるのが一般的です。
還付申告の場合は、確定申告期間(翌年2月16日から3月15日)よりも前から申告書を提出することが可能です(通常、翌年1月1日以降)。
これで、不動産売却に伴う確定申告の一連の手続きは完了となります。
こんな場合はどうする?不動産売却の確定申告に関する注意点
不動産売却の確定申告を進める中で、予期せぬ状況に直面することや、判断に迷うケースが出てくるかもしれません。ここでは、そうした場合にどのように対処すればよいか、いくつかの注意点を解説します。
確定申告の期間を過ぎてしまった場合の対処法とは?
法定申告期限は原則として、所得があった年の翌年の2月16日から3月15日までです。
しかし、うっかり忘れていた、あるいは事情があって期限内に申告できなかったという場合もあるかもしれません。
もし申告期限を過ぎてしまった場合でも、放置してはいけません。
気づいた時点でできるだけ速やかに「期限後申告」として確定申告書を提出しましょう。
期限後申告のやり方自体は、通常の確定申告の手続きと基本的には同じです。
ただし、期限後申告を行うと、いくつかのペナルティが課される可能性があります。
主なものとしては、以下の2つがあります。
- 無申告加算税
納付すべき税額に対して、原則として50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合で課されます。
ただし、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、
この割合が5%に軽減されることがあります。 - 延滞税
納付すべき税金が期限までに納付されなかった場合に、
法定納期限の翌日から実際に納付する日までの日数に応じて課される利息に相当する税金です。
税率は年によって変動します。
これらのペナルティを最小限に抑えるためにも、期限を過ぎてしまったことに気づいたら、
一日でも早く自主的に申告・納税を行うことが重要です。
具体的なペナルティの計算や手続きについては、管轄の税務署に確認することをおすすめします。
確定申告の内容を間違えてしまった場合の修正・訂正のやり方
細心の注意を払って確定申告書を作成・提出したつもりでも、後になって計算ミスや記入漏れ、
あるいは適用できる控除の見落としなどに気づくことがあります。
そのような場合は、内容を訂正するための手続きを行う必要があります。
訂正のやり方は、状況によって2つの種類があります。
- 税額を少なく申告していた場合(追加で納税が必要な場合)
この場合は、「修正申告」という手続きを行います。誤りに気づいたら、
できるだけ早く正しい内容で修正申告を作成し、不足分の税額を納付します。
修正申告は、税務署から指摘を受ける前に行うことで、過少申告加算税が軽減される場合があります。 - 税額を多く申告していた場合(還付を受けたい場合や、納付した税金が多すぎた場合)
この場合は、「更正の請求」という手続きを行います。法定申告期限から原則として5年以内であれば、
更正の請求書を税務署に提出し、納め過ぎた税金の還付を求めることができます。
請求が認められると、過払い分の税金が還付されます。
どちらの場合も、誤りに気づいた時点で速やかに正しい内容で手続きを行うことが肝心です。
訂正申告書や更正の請求書の様式は税務署で入手できるほか、国税庁のウェブサイトからもダウンロードできます。「確定申告書等作成コーナー」でも作成可能な場合があります。
不明な点があれば、管轄の税務署に問い合わせて指示を仰ぎましょう。
夫婦共有名義の不動産を売却した場合の確定申告のやり方
売却した不動産が夫婦の共有名義になっているケースは少なくありません。
例えば、夫の持分が2分の1、妻の持分が2分の1といった具合です。
このような共有名義の不動産を売却した場合、確定申告はどのように行えばよいのでしょうか。
結論から言うと、不動産が共有名義である場合は、その持分に応じて譲渡所得をそれぞれ計算し、
夫婦それぞれが個別に確定申告を行う必要があります。
具体的には、まず不動産の売却価格、取得費、譲渡費用を、それぞれの持分割合に応じて按分します。
例えば、売却価格が4,000万円で、夫と妻の持分がそれぞれ2分の1だった場合、夫の売却価格は2,000万円、
妻の売却価格も2,000万円として計算します。同様に、取得費や譲渡費用も持分割合で按分します。
そして、按分後の金額を使って、夫と妻それぞれが個別に譲渡所得を算出し、
各自の確定申告書を作成して税務署に提出します。たとえ夫婦であっても、
一方がまとめて申告することはできません。
この際の確定申告のやり方や使用する申告書の様式は、
基本的には個人で単独所有の不動産を売却した場合と同様です。
それぞれが必要書類を準備し、申告・納税(または還付)の手続きを行います。
なお、後述する3,000万円特別控除などの特例は、要件を満たせば夫婦それぞれが適用を受けることが可能です。
その場合、夫婦それぞれが最大3,000万円ずつ、合計で最大6,000万円の控除を受けられる可能性があります。
共有名義不動産の売却は、計算がやや複雑になるため、間違いのないよう慎重に進めることが大切です。
知らないと損?不動産売却の確定申告で活用できる特例・控除
不動産を売却した際の確定申告では、税負担を軽減するための様々な特例や控除の制度が設けられています。
これらの制度を上手に活用するかどうかで、実際に納める税金の額が大きく変わってくることもあります。
ここでは、代表的な特例・控除についてご紹介します。
重要な点として、これらの特例の適用を受けるためには、原則として確定申告を行うことが必須条件となります。
3,000万円特別控除(居住用財産を譲渡した場合の特別控除)
マイホーム、つまりご自身が住んでいる家(居住用財産)を売却した場合に利用できる可能性のある代表的な特例です。この特例の最大のポイントは、所有期間の長短に関わらず、譲渡所得の金額から最高で3,000万円まで控除することができる点です。
例えば、譲渡所得が2,500万円だった場合、この特例を適用すれば課税譲渡所得は0円となり、所得税や住民税はかかりません。譲渡所得が4,000万円だった場合は、3,000万円を控除した残りの1,000万円が課税対象となります。
この特例の適用を受けるための確定申告のやり方としては、確定申告書に所定の事項を記載するとともに、
「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)」、売却した家屋や敷地に関する事項を記載した書類、そして売却した不動産に以前住んでいたことを証明するための書類(住民票の除票など)を添付して税務署に提出する必要があります。いくつかの適用要件がありますので、詳細は国税庁のウェブサイトなどで確認が必要です。
10年超所有軽減税率の特例
売却した年の1月1日時点で、所有期間が10年を超えているマイホームを売却した場合に、上記の3,000万円特別控除を適用した後の譲渡所得について、通常よりも低い税率で所得税・住民税が計算される特例です。
具体的には、課税譲渡所得のうち6,000万円以下の部分については税率が14.21%(所得税10.21%、住民税4%)、6,000万円を超える部分については通常の長期譲渡所得の税率(20.315%:所得税15.315%、住民税5%)となります(復興特別所得税を含む)。
この特例は、3,000万円特別控除と併用することが可能です。この特例を利用する場合の確定申告のやり方も、
申告書への必要事項の記載と、戸籍の附票の写しなど所有期間を証明する書類の添付が必要となります。
特定の居住用財産の買換え(交換)の特例
マイホームを売却し、新たにマイホームを購入(買換え)した場合、一定の要件を満たせば、
売却した不動産の譲渡益に対する課税を、買い換えた不動産を将来売却する時まで繰り延べることができる特例です。
この特例は、課税が免除されるわけではなく、あくまで将来に先送りされるという点に注意が必要です。
適用を受けるためには、売却代金が1億円以下であること、売却した年とその前後1年以内(合計3年間)に
新たなマイホームを購入することなど、細かな要件が定められています。
この特例の適用を受けるための確定申告のやり方も、税務署への届出や確定申告書への所定事項の記載、
必要書類の添付が求められます。
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除
相続または遺贈によって取得した被相続人(亡くなった方)の居住用財産(いわゆる空き家)を、
相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、かつ一定の要件を満たして売却した場合に、
譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できる特例です。
この特例は、増え続ける空き家問題への対策の一環として設けられました。
適用を受けるためには、売却する家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであること、
相続時から譲渡時まで事業用・貸付用・居住用として使用されていないこと、売却代金が1億円以下であること、
耐震リフォームをするか建物を取り壊して更地で売却することなどの要件があります。
この特例の確定申告のやり方も、他の特例と同様に、
確定申告書への記載と市区町村長が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」などの必要書類の添付が必要です。
不動産売却で損失が出た場合の損益通算と繰越控除
不動産を売却して利益が出る(譲渡所得がプラスになる)場合だけでなく、
残念ながら損失が出る(譲渡損失が生じる)ケースもあります。
このような譲渡損失が生じた場合でも、一定の要件を満たせば、
その損失を他の所得(例えば給与所得や事業所得など)と相殺(損益通算)することができます。
損益通算を行うことで、他の所得にかかる所得税や住民税が軽減される効果があります。
さらに、その年の損益通算でも控除しきれない損失額が残った場合には、
その損失を翌年以降最大3年間にわたって繰り越して、各年の所得から控除(繰越控除)することが可能です。
ただし、すべての不動産売却損失で損益通算や繰越控除ができるわけではありません。
特にマイホーム(居住用財産)の売却で
損失が出た場合に適用できる特例(「居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」や
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」)があり、それぞれ適用要件が異なります。
これらの適用を受けるための確定申告のやり方も、確定申告書にその旨を記載し、
所定の計算明細書や必要書類を添付して提出する必要があります。
※各特例・控除の適用には詳細な要件があります。
必ず国税庁のホームページ等で最新の情報を確認するか、税務署や税理士にご相談ください。
確定申告のやり方に関するFAQ
不動産売却後の確定申告に関して、多くの方が疑問に思う点やよくある質問をQ&A形式でまとめました。
ご自身の状況と照らし合わせながらご確認ください。
Q1. 確定申告の期間はいつからいつまでですか?
A1. 不動産を売却した年の所得に関する確定申告の期間は、原則として、その翌年の2月16日から3月15日までです。
この1ヶ月間が申告および納税の期間となります。ただし、還付申告(税金が戻ってくる申告)の場合は、
翌年の1月1日から申告書を提出することが可能です。申告期限日が土曜日、日曜日、祝日等にあたる場合は、
その翌日が期限となります。期限間際は税務署が大変混雑するため、早めの準備と提出を心がけましょう。
Q2. どこで確定申告の手続きをするのですか?
A2. 確定申告書は、申告を行う年の1月1日時点におけるご自身の住所地(住民票のある場所)を管轄する税務署に提出します。管轄の税務署がどこになるかは、国税庁のウェブサイトで確認することができます。提出方法としては、税務署の窓口へ直接持参するほか、郵送やe-Tax(電子申告)を利用する方法があります。e-Taxを利用すれば、インターネット経由でどこからでも提出が可能です。
Q3. 忙しくて自分で確定申告できない場合はどうすればいいですか?
A3. ご自身で確定申告のやり方を調べる時間がない、あるいは不動産売却に関する税務処理が複雑で難しいと感じる場合には、税理士に相談し、確定申告の代行を依頼することを検討しましょう。税理士に依頼すると費用はかかりますが、専門家による正確な申告が期待でき、計算ミスや書類の不備を防ぐことができます。また、適用できる特例や控除についてのアドバイスを受けられる可能性もあり、結果的に節税につながることもあります。特に不動産売却の案件を多く扱っている、経験豊富な税理士に依頼するのがおすすめです。
Q4. 確定申告書を間違えて提出してしまったら、どうすればよいですか?
A4. 既に解説した通り、確定申告書を提出した後に内容の誤りに気づいた場合は、修正・訂正の手続きを行うことができます。税額を少なく申告していた(追加で納税が必要な)場合は「修正申告」を、税額を多く申告していた(還付を受けたい、または納付した税金が多すぎた)場合は「更正の請求」という手続きを行います。気づいた時点で速やかに、管轄の税務署に相談し、正しいやり方で手続きを進めてください。放置しておくと、加算税や延滞税が課される場合があるので注意が必要です。
Q5. 確定申告をしないとどうなりますか?
A5. 不動産を売却して利益が出ており、確定申告が必要であるにもかかわらず、期限内に申告を行わなかった場合、ペナルティが科されることになります。まず、本来納めるべき税額に加えて「無申告加算税」が課されます。税務署の調査を受けてから期限後申告をした場合は税率が高くなることがあります。また、納付すべき税額がある場合は、法定納期限の翌日から実際に納付する日までの日数に応じて「延滞税」も発生します。 さらに、意図的に所得を隠蔽するなど悪質なケースと判断された場合には、より重い「重加算税」が課されたり、場合によっては脱税行為として刑事罰の対象となることもあります。不動産売却で利益が出た場合は、必ず確定申告のやり方を確認し、期限内に正しく申告・納税を行いましょう。
Q6. 確定申告に関する相談はどこでできますか?
A6. 確定申告のやり方に関する一般的な相談であれば、まずは住所地を管轄する税務署の窓口や電話相談センターで対応してもらえます。国税庁のウェブサイトにも多くの情報が掲載されており、「タックスアンサー」というQ&A形式の情報提供サービスも役立ちます。また、確定申告期間中には、税理士会が主催する無料相談会などが各地で開催されることもあります。 ただし、これらの相談窓口では、あくまで一般的な手続きや法令の解釈に関する説明が中心となります。個別の具体的な計算方法の指導や、どの特例を使えば最も有利になるかといった節税コンサルティングまでは行ってもらえない場合が多いです。より専門的で具体的なアドバイスや申告書の作成代行を希望する場合は、やはり税理士に個別に相談するのが最も確実な方法と言えるでしょう。
まとめ|不動産売却後の確定申告は専門家への相談も検討しよう
今回は、不動産売却後の確定申告について、基本的な知識から具体的なやり方、注意すべき点、
そして活用できる可能性のある特例・控除制度に至るまで、詳しく解説してまいりました。
不動産の売却という、人生における大きなライフイベントの後には、
確定申告というもう一つの重要な手続きが待っています。一見すると、税金の計算や専門用語が多く、
複雑で難解に感じられるかもしれません。しかし、この記事でご紹介したように、
一つ一つのステップを丁寧に確認し、必要な書類をきちんと準備していけば、
ご自身でも確定申告のやり方を理解し、手続きを進めることは十分に可能です。
とはいえ、不動産の確定申告は、売却した不動産の種類(マイホームなのか、投資用なのかなど)や所有期間、
売却に至った経緯、家族構成、そして適用できる可能性のある特例の有無など、
個々の状況によって計算方法や必要となる書類が大きく異なってきます。
そのため、専門的な知識が求められる場面も少なくありません。
「確定申告のやり方がどうしても分からない」「自分で計算してみたけれど、本当に合っているか不安だ」
「もっと有利な節税方法があるのではないか」といった疑問や不安を感じる場合には、決して無理をせず、
税務署の相談窓口を利用したり、税理士などの専門家に相談したりすることを強くおすすめします。
専門家に依頼することで、時間と手間を省けるだけでなく、正確な申告による安心感を得られ、
場合によってはより有利な税務処理が可能になることもあります。
この記事が、あなたが不動産売却後の確定申告手続きをスムーズに進めるための一助となれば幸いです。
参考文献
[1] 国税庁 – No.3302 マイホームを売ったときの特例 – https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
[2] 国税庁 – No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例 – https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3305.htm
[3] 国税庁 – No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例 – https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3355.htm
[4] 国税庁 – No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 – https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
[5] 国税庁 – No.3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例) – https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3370.htm
[6] 国税庁 – No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例) – https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3390.htm
[7] 国税庁 – 確定申告が必要な方 – https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm
[8] 国税庁 – 確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分) – https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/08.htm
[9] 国税庁 – 土地や建物を売ったとき(分離課税) – https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_1.htm
[10] 国税庁 – 申告と納税 – https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/09.htm