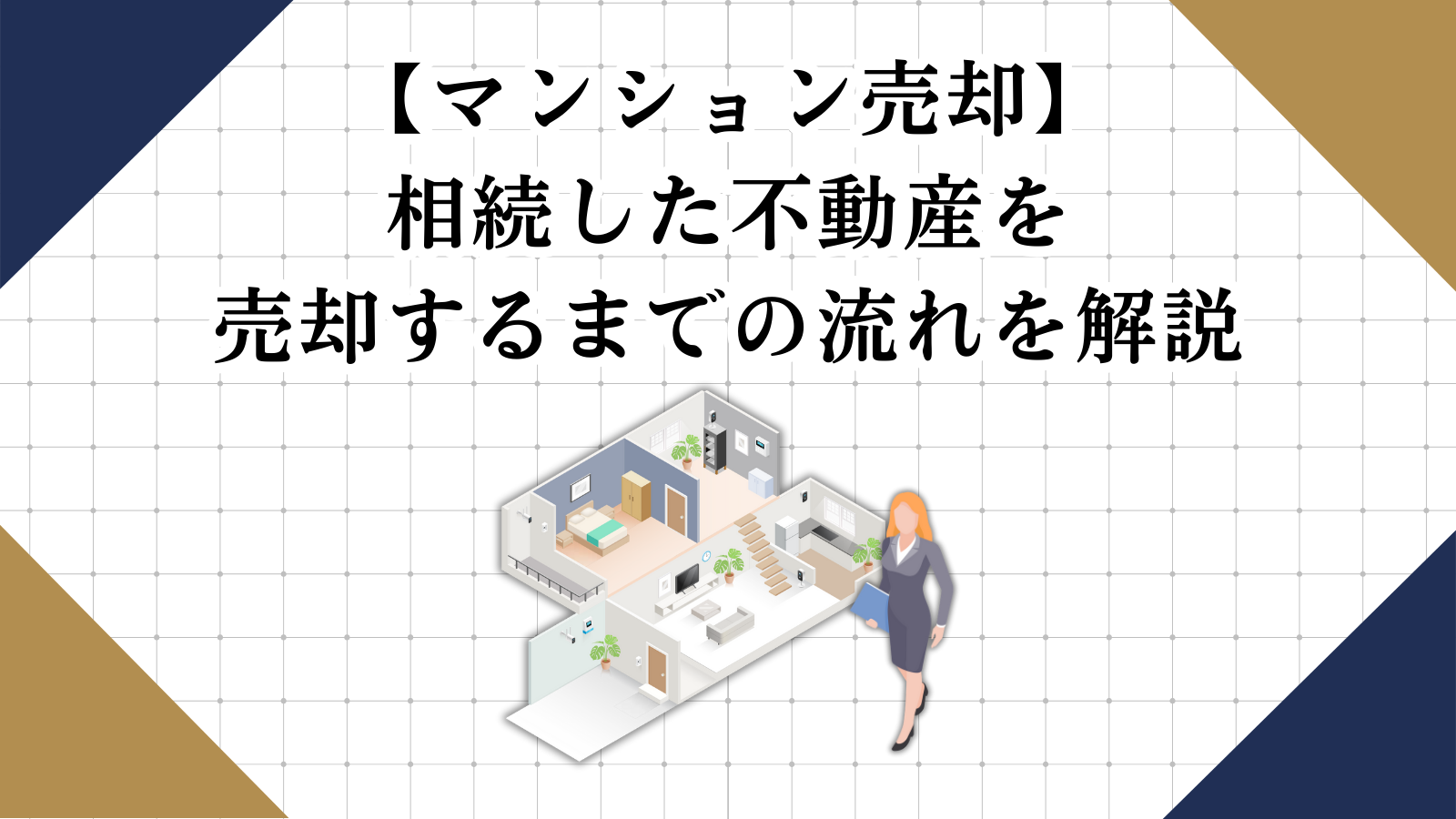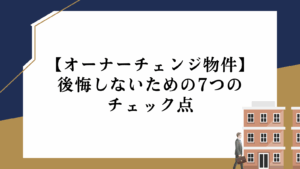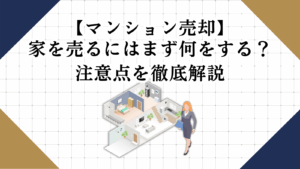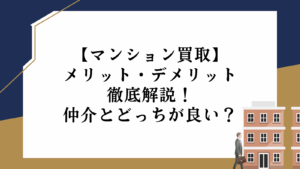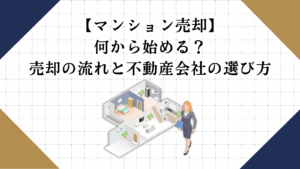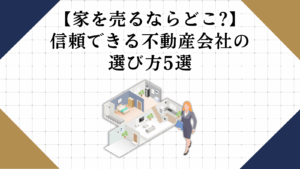親から不動産を相続したものの「何から手をつけていいか分からない」と悩んでいませんか?
この記事では、相続手続きの開始から不動産の売却まで、ステップごとに解説します。
相続不動産の売却は、流れや税金の特例を知らないと、数百万円単位で損をしてしまう可能性も。最後まで読むことで、やるべきことの全体像が明確になり、漠然とした不安は解消されているはずです。
相続不動産売却は3ステップ!全体の流れと期間の目安
相続した不動産の売却は、やることが多く複雑に感じられますが、全体の流れを把握すれば、一つひとつ着実に進めることができます。やるべきことは、大きく分けて「①相続手続き」「②売却活動」「③売却後の手続き」の3つのステップです。
まずは下の図で全体像を掴み、いつまでに何をすべきか確認しましょう。
①売却の準備(相続手続き)【期間の目安:2ヶ月〜1年】
相続が発生してから、不動産を売却できる状態に整えるまでの準備段階です。遺言書の確認から始まり、誰が何を相続するのかを相続人全員で話し合って決め、不動産の名義を相続人へ変更(相続登記)します。相続人の数や話し合いの進捗によって期間は大きく変動します。
②不動産の売却活動【期間の目安:3ヶ月〜6ヶ月】
不動産会社に売却を依頼し、買主を見つける段階です。査定から売却活動、売買契約、そして最終的な引き渡しまでが含まれます。不動産がスムーズに売れるかどうかは、物件の条件や市況によって左右されます。
③売却後の手続き(確定申告)【期間の目安:翌年2/16〜3/15】
不動産を売却して利益が出た場合、その翌年に税務署へ確定申告を行い、所得税を納税する必要があります。
名義変更(相続登記)までのステップ
不動産を売却するには、まず亡くなった方(被相続人)から相続人へ名義変更(相続登記)を完了させる必要があります。2024年4月1日から相続登記は義務化され、正当な理由なく怠ると過料が科される可能性もあります。売却の前提となる非常に重要な手続きですので、確実に進めましょう。
Step1:遺言書の有無を確認する
まず最初に、被相続人が遺言書を遺していないかを確認します。遺言書がある場合、原則としてその内容に従って遺産分割が行われるため、すべての手続きの基本となります。特に、法務局で保管されている自筆証書遺言や、公証役場で作成された公正証書遺言以外の遺言書(自宅で保管されていたものなど)が見つかった場合は、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。
Step2:相続人と相続財産を調査・確定する
遺言書がない場合、法律で定められた相続人(法定相続人)を確定させる必要があります。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を取り寄せ、誰が相続人になるのかを正確に把握します。同時に、売却対象の不動産をはじめ、預貯金や有価証券など、相続財産全体を調査し、財産目録を作成します。
Step3:相続人全員で遺産分割協議を行う
相続人が複数いる場合は、誰がどの財産を相続するのかを全員で話し合う「遺産分割協議」を行います。ここで不動産を売却することが決まった場合、一般的には「換価分割(かんかぶんかつ)」という方法がとられます。
換価分割とは?
不動産を売却して現金化し、その現金を相続分に応じて分配する方法です。不動産そのものを分ける(現物分割)のは難しいため、公平に分けやすい換価分割は、相続不動産の売却で多く用いられる手法です。
Step4:相続登記を行い売却準備を整える
遺産分割協議で不動産を相続する人が決まったら、その内容を証明する「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名・実印を押印します。この協議書と必要書類を揃えて、法務局で不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する「相続登記」を申請します。
前述の通り、相続登記は相続を知った日から3年以内に行うことが義務付けられています。手続きは複雑なため、司法書士に依頼するのが一般的です。
失敗しない相続不動産の売却活動と契約の流れ
相続登記が完了し、不動産の名義がご自身のものになったら、いよいよ売却活動に移ります。大切な資産を少しでも良い条件で、そしてトラブルなく売却するためには、信頼できる不動産会社をパートナーに選ぶことが何よりも重要です。
不動産会社に査定を依頼する【会社選び3つのポイント】
まずは、その不動産がいくらで売れそうか、不動産会社に査定を依頼します。このとき、1社だけでなく複数の会社に依頼し、査定価格や担当者の対応を比較検討しましょう。
【不動産会社選びの3つのポイント】
- 相続物件の売却実績が豊富か
- 相続ならではの税務や法務に詳しい会社は頼りになります。
- 査定価格の根拠が明確か
- なぜその価格なのか、周辺の取引事例などを用いて具体的に説明してくれるかを確認しましょう。
- 担当者との相性が良いか
- 親身に相談に乗ってくれ、密に連絡が取れる信頼できる担当者かを見極めることが大切です。
媒介契約を結び、売却活動をスタートする
売却を依頼する不動産会社が決まったら、「媒介契約」を結びます。契約には3つの種類があり、それぞれ特徴が異なります。
- 一般媒介契約
- 複数の不動産会社に同時に依頼できる。
- 専任媒介契約
- 依頼できるのは1社のみ。不動産会社に販売状況の報告義務がある。
- 専属専任媒介契約
- 依頼は1社のみで、自分で買主を見つけることもできないが、手厚いサポートが受けられる。
ご自身の状況に合わせて最適な契約形態を選び、いよいよ売却活動がスタートします。
購入希望者と売買契約を締結する
不動産会社が広告活動などを行い、購入希望者が見つかると、物件の内覧対応などを行います。価格などの条件交渉がまとまれば、買主と「売買契約」を締結します。契約時には、物件の詳細や法的な制限などを記した「重要事項説明書」の説明を受け、買主から手付金を受領します。
残代金決済と物件の引き渡しを行う
契約から約1ヶ月後、金融機関などで買主から手付金を除いた残りの売買代金を受け取ります(決済)。同時に、司法書士の立ち会いのもと、所有権を買主へ移転する登記手続きを行い、物件の鍵を引き渡します。これで、不動産の売却手続きはすべて完了です。
まとめ
今回は、相続した不動産を売却するまでの一連の流れを、手続き、税金、注意点に分けて解説しました。
- 相続不動産の売却は「準備」「売却」「申告」の3ステップで進む。
- 売却の前提として、遺産分割協議と相続登記(名義変更)
- 信頼できる不動産会社や専門家をパートナーに選ぶことが重要。
相続と売却の手続きは、時間も労力もかかります。しかし、一つひとつのステップを計画的に、そして着実に進めることで、トラブルなく大切な資産を次の形に変えることができます。
まずは、本記事を参考に「遺言書の確認」や「相続人の確定」から始めてみてはいかがでしょうか。この記事が、あなたのスムーズな不動産売却の一助となれば幸いです。