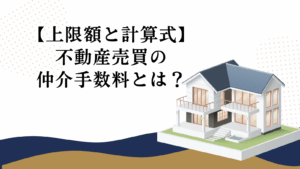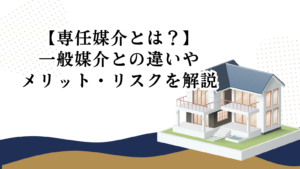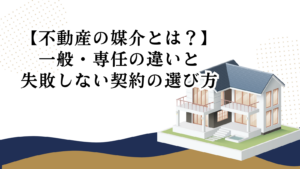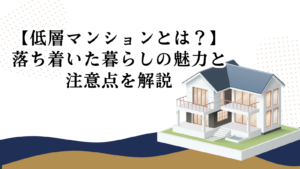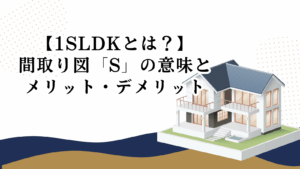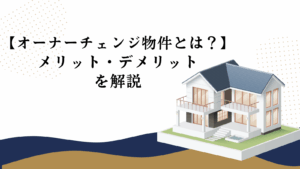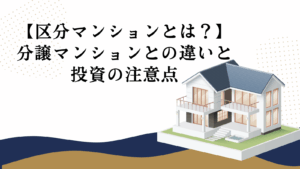【不動産相場の調べ方】プロ直伝の調査方法と価格影響要素一覧
「この不動産、本当に適正価格なの?」
「不動産の相場って、どうやって調べればいいんだろう…」
「マンションを売却したいけど、いくらで売り出せばいいのか見当がつかない」
「インターネットで色々調べてみたけど、どの情報を信じればいいの?」
「不動産会社の査定額がバラバラで、何を基準にすればいいのか混乱している」
このような悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不動産の購入や売却を検討する際、誰もが直面するのが「価格の妥当性」という大きな疑問です。相場を知らないまま取引を進めてしまうと、気づかぬうちに損をする可能性があります。高値掴みをしてしまったり、安く売却してしまったりと、大切な資産に関わることだけに、不安は大きいものです。
この記事では、不動産(特にマンション)の購入や売却を考えている皆様が、ご自身で物件の相場を調べ、適正価格を判断できるようになるための具体的な調査方法をステップごとに徹底解説します。参考にできる資料や情報の取得方法から、価格に影響を与える要素まで網羅し、後悔のない不動産取引をサポートします。
(※本記事は、2025年5月19日現在の情報を基に解説しています。)
長年、不動産の適正な価値を評価する業務に携わる中で、一般の方が「相場」というものにいかに不安を感じているかを目の当たりにしてきました。不動産の価格は専門的で分かりにくいというイメージがあるかもしれませんが、実は誰でもアクセスできる情報や、基本的な調査の「仕方」を理解すれば、ある程度の相場観を養うことは可能です。
私自身、駆け出しの頃は不動産鑑定評価を行う上で、どのようにしてその物件の「適正価格」を導き出すのか、情報の収集から分析まで試行錯誤の連続でした。特に、市場性の高い居住用マンションの評価では、いかにして実際の取引事例や市場の動向を正確に把握するかが鍵となります。インターネットが普及した現在でも、信頼性の高い情報を選び抜き、多角的に分析する重要性は変わりません。
本記事では、私が実務で培ってきた相場調査のノウハウを、皆様にも分かりやすくお伝えし、不動産取引における不安解消のお手伝いをさせていただきます。この記事を通して、皆様が自信を持って不動産取引に臨めるようになることを願っています。
なぜ重要?不動産(マンション)の「相場」を知ることが取引成功の第一歩
不動産取引において、その物件の「相場」を知ることは、単なる参考情報ではありません。むしろ、取引を成功させるための土台であり、最も重要な準備と言えるでしょう。相場を知ることで、様々なメリットを享受し、リスクを回避することが可能になります。
適正価格での購入・売却は、資産形成の基本
不動産は多くの方にとって人生で最も高価な買い物、あるいは売却になるでしょう。その取引価格が相場からかけ離れている場合、購入であれば「高値掴み」、売却であれば「安値売却」となり、不当な損失を被る可能性があります。適正な相場を把握し、その範囲内で取引を行うことは、ご自身の資産を守り、将来的な資産形成計画を狂わせないために不可欠です。
例えば、マンションを購入する場合、適正価格で購入できれば、将来的な売却時や賃貸に出す際に、購入価格とのバランスを考慮した計画が立てやすくなります。逆に、相場より著しく高い価格で購入してしまうと、市況が悪化した際に資産価値が大幅に下落するリスクが高まります。売却の場合も同様に、相場を理解していれば、早期売却を優先するのか、希望価格での売却を目指すのかといった戦略を適切に判断できます。
不動産会社との対等な交渉のための武器になる
不動産取引においては、多くの場合、不動産会社が間に入ります。不動産会社は市場情報や取引事例を豊富に持っていますが、買主や売主が相場に関する知識を持たずに交渉に臨むと、不動産会社の提案を鵜呑みにしてしまうことになりかねません。
ご自身で客観的な相場観を持つことで、不動産会社から提示された査定価格や売り出し価格、あるいは購入希望価格の妥当性を冷静に判断できるようになります。
例えば、売却査定で提示された価格がご自身の調査した相場とかけ離れている場合、なぜそのような価格になったのか、その根拠を具体的に質問することができます。また、購入交渉の際も、周辺の類似物件の相場を把握していれば、「この物件のこの条件なら、この価格が適正ではないか」といった具体的な根拠を示しながら交渉を進めることが可能になります。相場を知ることは、不動産会社とのコミュニケーションを円滑にし、より有利な条件で取引を進めるための強力な武器となるのです。
具体的な資金計画やライフプランニングに不可欠
不動産の購入や売却は、その後の生活やライフプランに大きな影響を与えます。相場を把握することで、より具体的かつ現実的な資金計画を立てることができます。
マンション購入の場合、相場を知ることで、無理のない購入予算を設定し、頭金や住宅ローン借入額の目安を立てることができます。また、購入後の管理費や修繕積立金なども考慮に入れた長期的な資金計画が可能になります。売却の場合も、相場を把握していれば、売却によって得られるおおよその手取り額を予測し、その資金を次の住まいの購入費用や老後の資金、あるいはその他の目的にどのように充てるかといった具体的なライフプランを立てることができます。相場は、将来を見据えた賢明な意思決定を行うための基礎情報となるのです。
「知らなかった」では済まされない!情報格差による後悔を防ぐ
不動産取引は、専門的な情報が多く、一般の方がアクセスしにくい情報も存在するため、情報が偏在しやすいという側面があります。不動産のプロと一般の方の間には、どうしても情報格差が生じがちです。この情報格差が、不利益な取引につながる可能性もゼロではありません。
しかし、現代ではインターネットの普及により、以前に比べて多くの情報にアクセスできるようになりました。国土交通省が提供する取引価格情報や、大手不動産ポータルサイトに掲載されている物件情報など、ご自身で調べられる情報はたくさんあります。これらの情報を活用し、自ら積極的に情報を得る努力をすることで、情報格差を埋め、不利益な取引を未然に防ぐことができます。「知らなかった」という理由で後悔しないためにも、相場を調べるという行為は非常に重要なのです。
【ステップ別】不動産(マンション)相場の調べ方・調査の仕方
ここでは、不動産の相場を自分で調べるための具体的な「仕方」を、ステップを追って詳しく解説します。これらのステップを順番に進めることで、客観的な相場観を養うことができます。
ステップ1:調査対象となる不動産(マンション)の情報を正確に把握する
このステップでは、相場調査の基礎となる物件情報の整理を行います。
相場調査を始める前に、まず調査対象となる不動産の情報を正確に整理することが重要です。どのような物件の相場を知りたいのかが曖昧だと、適切な情報を収集できません。以下の項目について、可能な限り具体的に把握しておきましょう。
- 物件種別: マンション、一戸建て、土地
- 所在地: 正確な住所、最寄り駅、最寄り駅からの徒歩分数(駅距離は価格に大きく影響します。複数の路線が利用できる場合は、それぞれの駅からの距離や利便性も確認します。)
- 築年数: 建物が完成してからの経過年数
- 構造: 鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)、鉄骨造(S造)、木造など
- 専有面積: マンションの場合、壁芯面積(隣戸との壁の中心線で囲まれた面積)や登記簿面積(壁の内側の面積)
- 間取り: 1R、1DK、3LDKなど
- 部屋の方角: 南向きは日当たりが良いとされ人気
- 階数: 高階層の方が眺望や日当たり、騒音が少なく人気
- 特記事項: リフォームやリノベーションの履歴とその内容、角部屋か中部屋か、最上階か、ルーフバルコニーの有無、ペット飼育の可否、駐車場や駐輪場の状況など
これらの情報を整理することで、後続のステップで類似物件を検索する際に、条件を絞り込みやすくなります。
ステップ2:オンラインツールを活用した相場調査
このステップでは、インターネットを用いて調査できる内容をまとめています。
インターネット上には、不動産の相場を調べるのに役立つ様々なツールがあります。これらのツールを効果的に活用することで、手軽に大まかな相場観を掴むことができます。
大手不動産ポータルサイト(SUUMO、LIFULL HOME’S、athomeなど)での類似物件検索
まずは、現在市場で「売り出し中」の物件情報を調べてみましょう。SUUMO(スーモ)、LIFULL HOME’S(ライフルホームズ)、athome(アットホーム)といった大手不動産ポータルサイトでは、希望エリアや物件の条件を入力して検索することで、現在売りに出されている類似物件の価格情報を一覧できます。
これらのサイトで、ステップ1で整理した条件(エリア、最寄り駅からの距離、築年数、専有面積、間取りなど)に近い物件を複数探し、それぞれの「売り出し価格」を確認します。単に価格を見るだけでなく、1平方メートルあたりの価格である「㎡単価」や、3.3平方メートルあたりの価格である「坪単価」も比較すると、面積が異なる物件同士でも価格水準を比較しやすくなります。
特にマンションの場合は、同じマンション内で現在売り出し中の部屋がないかを確認することも重要です。同じマンション内の過去の成約事例や現在の売り出し事例は、そのマンション自体の人気や管理状況なども反映しているため、最も参考になる情報の一つと言えます。
ただし、ポータルサイトに掲載されている価格はあくまで「売り出し価格」であり、実際に買主と売主の間で合意に至った「成約価格」とは異なる場合が多いことに注意が必要です。売り出し価格は売主の希望価格であり、実際の成約価格は交渉によって下がることもあります。そのため、ポータルサイトの情報だけでは、実際の取引価格を正確に把握することは難しい場合があります。
不動産取引価格情報検索(国土交通省)で実際の「成約価格」を調査
ポータルサイトの「売り出し価格」に対し、実際にどのような価格で不動産が取引されているのかを知るには、国土交通省が提供する「不動産取引価格情報検索」が非常に役立ちます。
これは、不動産取引を行った際に報告された価格情報を集計し、個人が特定できないように加工した上で公開しているデータベースです。エリア(市区町村)、時期(四半期ごと)、不動産の種類(宅地、宅地(土地と建物)、マンション等)で絞り込んで検索すると、過去に実際に取引された不動産の「成約価格」とその概要(最寄り駅からの距離、面積、間取り、築年数など)を確認することができます。
この情報を活用することで、ポータルサイトだけでは分からなかった「実際の取引価格」の水準を知ることができます。マンションの場合は、「マンション等の所在する地域」として市区町村名や最寄り駅などが表示されますが、具体的なマンション名までは特定できません。しかし、同じようなエリアで、築年数や広さが近いマンションがどのくらいの価格で取引されているかを知る上で、非常に信頼性の高い情報源となります。
検索結果には、「取引総額」の他に「㎡単価」も表示されるため、異なる広さの物件同士を比較する際にも便利です。ただし、ここに掲載されている情報も、個別の物件の詳しい状態(リフォームの有無や程度、部屋の向き、階数など)までは分からないため、あくまで参考情報として活用することが重要です。また、情報の更新にはタイムラグがあることにも留意が必要です。
AI査定サイト・アプリの活用法と注意点
最近では、オンラインで物件情報を入力するだけで、AIが自動的に概算の査定価格を算出してくれるサービスも増えています。大手不動産会社や不動産情報サイトなどが提供しており、スマートフォンアプリで手軽に利用できるものもあります。
これらのAI査定は、過去の取引事例データや現在の売り出し事例、物件の基本情報などを基に統計的に価格を算出するため、非常にスピーディーに大まかな価格を知ることができます。特に、複数のサイトでAI査定を行ってみることで、それぞれの算出根拠の傾向の違いなどを比較することも可能です。
しかし、AI査定はあくまでも簡易的な「机上査定」のレベルであり、個別性を十分に反映することは難しいという限界があります。物件ごとの詳しい状態(リフォームの質、設備のグレード、眺望、騒音など)、周辺環境の微細な違い、売主の売却理由や希望条件、市場の短期的な変動といった要素は、AI査定では正確に把握できません。そのため、AI査定で算出された価格を鵜呑みにせず、あくまで参考の一つとして捉え、次のステップで紹介する他の情報源と組み合わせて活用することが重要です。
ステップ3:公的データ・統計情報を参考にする
オンラインツール以外にも、不動産の相場や価値判断の参考になる公的なデータや統計情報があります。これらは直接的な取引価格を示すものではありませんが、土地の評価や市場全体の動向を理解する上で役立ちます。
REINS Market Information(レインズ・マーケット・インフォメーション)の活用
REINS(レインズ)とは、Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)の略称で、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステムです。不動産会社は、媒介契約を結んだ物件情報をこのレインズに登録することが義務付けられており、登録された情報は全国の不動産会社間で共有されます。
レインズには、現在売り出し中の「登録物件情報」だけでなく、すでに取引が成立した「成約事例情報」も蓄積されています。特に成約事例情報は、実際の取引価格に関する詳細なデータが含まれており、不動産鑑定士や不動産会社が相場を調査する際に非常に重要な情報源として活用しています。
このレインズの情報は、一般の個人が直接閲覧することはできません。しかし、不動産会社に売却や購入の相談をする際に、担当の不動産会社を通じて、希望するエリアや条件に近い物件の成約事例データを提示してもらうことが可能です。不動産会社が査定価格を算出する際の根拠としても、レインズの成約事例が用いられます。信頼できる不動産会社を見つけ、レインズの情報を活用させてもらうことも、より正確な相場情報を得るための有効な「仕方」の一つです。
地価公示価格・都道府県地価調査価格(土地の相場)
地価公示価格は、国土交通省が毎年1月1日時点の標準的な土地の1平方メートルあたりの価格を公示するものです。都道府県地価調査価格は、各都道府県が毎年7月1日時点の基準地について調査するもので、地価公示価格を補完する役割を果たします。
これらの価格は、主に更地の土地価格を示すものであり、建物(特にマンションの専有部分)の取引価格を直接的に表すものではありません。しかし、マンションが建っている土地の価値を把握する上で参考になります。特に、同じエリアにある複数のマンションの価格水準を比較する際に、そのマンションが建つ土地の地価水準を考慮に入れることで、より多角的な視点から相場を分析することができます。また、これらの地価は不動産鑑定士が土地の評価を行う際の規準としても用いられます。
路線価・固定資産税評価額(税務上の評価額)
路線価は、国税庁が公表する、主要な道路に面した宅地の1平方メートルあたりの価格です。主に相続税や贈与税を計算する際の基準となります。固定資産税評価額は、市町村(東京都23区は都)が算定する、固定資産税や都市計画税、不動産取得税、登録免許税などを計算する際の基準となる土地や建物の評価額です。
これらの価格も、地価公示価格と同様に、市場での実際の取引価格とは異なります。公的な評価額であり、市場価格よりも低く評価されるのが一般的です。しかし、同じエリア内の複数の物件を比較する際に、これらの評価額の相対的な水準を参考にすることで、物件ごとの価値の序列や傾向を掴むことができる場合があります。例えば、路線価が高い場所にある物件は、そうでない場所にある物件に比べて、一般的に市場価格も高くなる傾向があるといったように、相対的な比較指標として活用できます。固定資産税評価額は、固定資産税評価証明書を取得することで確認できます。
ステップ4:複数の不動産会社に査定を依頼する
自分でオンラインツールや公的データを使ってある程度の相場観を養った後は、実際に複数の不動産会社に査定を依頼してみましょう。これが、より実践的な相場情報を得るための重要なステップです。
不動産会社が行う査定には、大きく分けて「机上査定(簡易査定)」と「訪問査定(詳細査定)」があります。
- 机上査定
- 物件の基本情報(所在地、広さ、築年数など)を伝えるだけで、過去の取引事例や現在の売り出し事例、市場動向などから概算の査定価格を算出してもらう方法です。短時間で複数の会社から査定結果を得たい場合に適しています。ステップ2のAI査定に近いイメージですが、不動産会社の担当者が介在するため、より市場の実情に近い価格が出やすい傾向があります。
- 訪問査定
- 不動産会社の担当者が実際に物件を訪問し、室内の状態、リフォームの有無、設備の状況、日当たり、眺望、騒音といった物件固有の詳細や、マンション全体の管理状況、周辺環境などを詳しく調査した上で、査定価格を算出してもらう方法です。机上査定よりも手間はかかりますが、物件の個別性をより反映した、精度が高い査定価格を得られます。
査定を依頼する際は、最低でも3社程度の異なる不動産会社に依頼することをおすすめします。複数の会社に依頼することで、それぞれの査定価格や算出根拠、さらには物件の強みや弱みに対する見方、どのような販売戦略を考えているのかなどを比較検討できます。査定価格が大きく異なる場合は、その理由をしっかり質問し、納得のいく説明をしてくれる不動産会社を選びましょう。査産会社とのコミュニケーションを通じて、ご自身の物件が市場でどのように評価されるのか、より具体的なイメージを持つことができます。
ステップ5:現地調査と周辺環境の確認
机上での調査だけでなく、実際に現地を訪れ、周辺環境を自分の目で確認することも非常に重要です。インターネット上の情報やデータだけでは分からない、不動産の持つ「雰囲気」や「住み心地」に関わる要素は、価格にも影響を与えることがあります。
調査対象のマンションやその周辺を実際に歩いてみましょう。最寄り駅からの道のり、周辺の商業施設(スーパー、コンビニ、飲食店など)や公共施設(役所、図書館、病院など)の利便性、公園や緑地の有無、学校区の評判、地域の治安などを肌で感じてみてください。昼と夜、平日と休日で雰囲気や人の流れ、騒音レベルなどが変わることもあるため、可能であれば複数の時間帯や曜日に訪れるとより参考になります。
また、周辺で「売マンション」や「売地」などの看板が出ていないかもチェックしてみましょう。これらの看板が出ている物件があれば、その地域の売り出し状況を把握するヒントになります。ただし、看板に記載されている連絡先に直接問い合わせる際は、信頼できる不動産会社かどうかを事前に確認するようにしましょう。
現地調査では、インターネット上の情報だけでは得られない「生きた情報」を収集できます。その物件や地域で生活するイメージを具体的に持つことができ、これが購入や売却の判断、そして価格の妥当性を判断する上で役立ちます。
【情報源一覧】参考にできる資料とデータの取得方法
これまでに紹介した相場調査のステップで活用できる、具体的な情報源を改めて一覧で整理します。これらの資料やデータを適切に取得し、組み合わせることで、より精度の高い相場観を養うことができます。
オンラインツール
- 不動産ポータルサイト(SUUMO、HOME’S、athome 等)
- 取得方法:各ウェブサイトにアクセスし、希望条件で検索
- 内容:現在「売り出し中」の物件の価格、物件概要、写真など
- 用途:市場に出ている物件の価格水準、競合物件の状況把握
- 不動産取引価格情報検索(国土交通省)
- 取得方法:国土交通省のウェブサイトにアクセスし、検索ツールを利用
- 内容:過去に「成約した」不動産の取引価格とその概要
- 用途:実際の取引価格水準の把握、より現実的な相場観の形成
- 各社AI査定サービス
- 取得方法:不動産会社や不動産情報サイトのウェブサイト・アプリで物件情報を入力
- 内容:物件の基本情報に基づいた概算の査定価格
- 用途:手軽な価格目安の把握、複数のサービスの比較
- マンション相場情報サイト(マンションレビュー、東京カンテイのデータ等)
- 取得方法:各ウェブサイトにアクセス(会員登録が必要な場合あり)
- 内容:特定のマンションの過去の売買事例や賃貸事例、参考価格、ランキング情報など
- 用途:特定のマンションや周辺マンションの相場情報の深掘り
公的機関・団体提供データ
- 地価公示・都道府県地価調査(国土交通省)
- 取得方法:国土交通省のウェブサイトにアクセス
- 内容:標準地・基準地の土地の価格
- 用途:対象不動産が建つ土地の評価や地域全体の地価水準の把握
- 路線価(国税庁)
- 取得方法:国税庁のウェブサイト「財産評価基準書」にアクセス
- 内容:相続税や贈与税算定の基準となる道路に面した土地の価格
- 用途:税務上の評価額の把握、地域内の相対的な土地評価の参考
- 固定資産税評価証明書(市区町村)
- 取得方法:物件所在地の市町村役場(東京都23区は都税事務所)の税務課などで取得を申請(所有者またはその委任状を持った代理人)
- 内容:固定資産税算定の基準となる土地・家屋の評価額
- 用途:税務上の評価額の把握、公的な評価額の参考
- REINS Market Information(不動産会社経由)
- 取得方法:不動産会社に売却や購入の相談をする際に、担当者を通じて情報の提供を依頼
- 内容:不動産流通機構に登録された物件情報(売り出し中、成約事例)
- 用途:より詳細で最新の成約事例データの入手
不動産会社提供資料
- 査定報告書
- 取得方法:不動産会社に査定を依頼する
- 内容:不動産会社が算出した査定価格とその根拠(周辺事例、市場動向など)、販売戦略案
- 用途:プロによる個別物件の評価、複数の会社の評価比較
- 周辺売出事例・成約事例リスト
- 取得方法:不動産会社に相談する際に提供を依頼
- 内容:対象物件周辺の類似物件の売り出し事例や成約事例の詳細
- 用途:査定根拠の確認、より詳細な個別事例の把握
その他
- 不動産関連ニュース、業界レポート
- 取得方法:主要経済紙、不動産専門紙、シンクタンクのレポートなどを参照
- 内容:市場全体の動向、特定のエリアや物件種別のトレンド、金利動向など
- 用途:マクロ的な市場環境の理解、価格変動要因の把握
- 地域情報誌、専門家(不動産鑑定士など)の意見
- 取得方法:地域の情報誌購読、不動産鑑定士に相談(有料の場合あり)
- 内容:地域に密着した情報、専門家による客観的な評価やアドバイス
- 用途:地域特有の事情の理解、より専門的な視点からの意見参考
これらの情報源を単独で利用するのではなく、複数組み合わせて多角的に分析することが、より正確な相場観を養うための鍵となります。
不動産の価格を左右する!主な影響要素を徹底解説
不動産の価格は、単純な立地や広さだけで決まるわけではありません。様々な要因が複雑に絡み合って形成されます。ここでは、不動産価格に影響を与える主な要素を詳しく解説します。これらの要素を理解することで、なぜある物件が高く、ある物件が安いのか、その理由をより深く理解できるようになります。
【立地条件】最も重要な価格決定要因
不動産の価格を決定する上で、最も重要かつ影響力が大きい要素の一つが「立地条件」です。「不動産は立地が命」と言われるほど、その土地や建物が存在する場所は価格に直結します。
- 最寄り駅からの距離、複数路線利用の可否
- 駅に近ければ近いほど、また複数の路線が利用できアクセスが良いほど、一般的に価格は高くなります。特に都心へのアクセス時間は重要な判断材料となります。
- 周辺の商業施設・公共施設(スーパー、病院、学校、公園など)の充実度
- 日常の買い物や生活に必要な施設が近くにあるか、子育て世帯であれば評判の良い学校区かなど、周辺環境の利便性や住みやすさは価格に影響します。
- 治安
- その地域の治安が良いか悪いかは、住環境としての魅力に直結し、価格にも反映されます。
- ハザードマップ上の安全性
- 洪水、地震、土砂崩れなどの自然災害リスクが低いエリアは、価格が安定しやすい傾向があります。自治体が公表しているハザードマップで事前に確認することが重要です。
- 将来の再開発計画
- 駅前の再開発や大型商業施設の建設など、将来的に周辺環境が向上する見込みがあるエリアは、資産価値の上昇が期待され、現在の価格にも影響を与えることがあります。
【物件自体の特性】
立地条件に加えて、物件そのものが持つ特性も価格に大きく影響します。
建物
- 築年数
- 新しい建物ほど価値が高いとされる傾向があります。ただし、築年数が経過していても、適切なメンテナンスやリフォームが行われている場合は、価格が維持されたり、価値が見直されたりすることもあります。
- 構造(耐震性)
- 新耐震基準を満たしているかなど、建物の構造や耐震性は安全性の観点から非常に重要です。
- 施工会社、ブランド
- 信頼できる大手施工会社が建てた物件や、有名なデベロッパーが開発したブランドマンションは、品質やデザイン、管理体制などが評価され、価格に反映されることがあります。
- マンションの場合
- 総戸数: 大規模マンションは共用施設が充実している傾向がありますが、管理組合運営や修繕工事の合意形成に時間がかかる場合もあります。規模によってメリット・デメリットがあり、価格への影響も一概には言えません。
- 管理体制(管理会社、修繕積立金の状況、管理規約): 管理会社が適切に建物を管理しているか、長期修繕計画がしっかり立てられ、修繕積立金が十分に積み立てられているか、管理規約が居住者にとって適切かなどは、マンションの維持管理状況や将来性に直結し、価格に大きく影響します。これらの状況が良好なマンションは、築年数が経過していても価値が維持されやすいです。
住戸(マンションの場合)
- 階数
- 一般的に高層階ほど眺望が良く、騒音の影響も少ないため、価格が高くなる傾向があります。
- 方角
- 南向きは日当たりが良いため人気が高く、価格も高くなる傾向があります。
- 角部屋か中部屋か
- 角部屋は窓が多く、採光や通風が良いことが多いため、価格が高くなる傾向があります。
- 日当たり・眺望・風通し
- 個別の住戸の日当たり、部屋からの眺め、風通しの良さといった快適性に関わる要素は、価格に直接的に影響します。
- 専有面積
- 広さに対する需要は高く、一般的に専有面積が広いほど価格も高くなります。ただし、㎡単価で比較すると、広い部屋よりコンパクトな部屋の方が㎡単価が高くなる傾向があるなど、広さと価格の関係は一概には言えません。
- 間取りの使いやすさ、収納量
- 生活動線を考慮した使いやすい間取りや、十分な収納スペースがあるかどうかも、居住者にとっての利便性に関わり、価格に影響を与えることがあります。
設備
- キッチン、浴室、トイレなどのグレードや新しさ
- 住宅設備のグレードが高く、比較的新しい場合は、快適性が向上し、価格に反映されることがあります。
- セキュリティ設備
- オートロック、防犯カメラ、インターホンなどのセキュリティ設備が充実しているマンションは、安全性が高いと評価され、価格に影響します。
- インターネット環境
- 光ファイバーが導入されているなど、快適なインターネット環境が整備されているかも、現代においては重要な要素です。
- 共用施設(マンションの場合:ラウンジ、ゲストルーム、ジムなど)
- タワーマンションなどで見られる充実した共用施設は、付加価値となり価格に影響を与えることがあります。ただし、共用施設の維持管理にはコスト(管理費・修繕積立金)がかかるため、そのバランスも考慮が必要です。
状態
- リフォーム・リノベーションの有無と内容
- リフォームやリノベーションによって室内が綺麗になっていたり、設備が新しくなっていたりする場合は、その内容に応じて価格が上乗せされることがあります。
- メンテナンス状況
- 定期的なメンテナンスが行き届いているか、建物の老朽化が進んでいないかなども、建物の寿命や快適性に関わり、価格に影響します。
- 心理的瑕疵の有無
- いわゆる「事故物件」のように、過去に事件や事故があったなど、買主の住み心地に心理的な影響を与える可能性がある「心理的瑕疵」がある場合は、価格が相場よりも大幅に安くなることが一般的です。
【市場動向・経済状況】
個別の物件要因だけでなく、不動産市場全体や経済状況も価格に大きな影響を与えます。
- 金利動向(住宅ローン金利)
- 住宅ローンの金利が低い場合は、住宅購入の負担が軽減されるため、不動産市場が活発になり、価格を押し上げる要因となります。逆に金利が上昇すると、購入意欲が減退し、価格が下がる可能性があります。
- 景気
- 経済全体が好調であれば、個人の所得が増え、不動産への投資意欲も高まるため、価格が上昇しやすい傾向があります。不景気の場合はその逆の動きになることが多いです。
- 不動産市場の需給バランス(売り手市場か買い手市場か)
- 買いたい人(需要)が多く、売りたい物件(供給)が少ない「売り手市場」では価格は上昇しやすく、逆に需要が少なく供給が多い「買い手市場」では価格は下落しやすい傾向があります。
- 税制(不動産取得税、固定資産税、譲渡所得税など)
- 不動産に関わる税制の変更は、購入や売却にかかるコストに影響するため、市場全体の動きや価格に影響を与えることがあります。
- 法改正
- 建築基準法や都市計画法、あるいはマンション管理適正化法など、不動産に関連する法改正も、建物の建築や維持管理、あるいは不動産取引のルールに影響を与え、間接的に価格に影響を与える可能性があります。
【取引条件・その他】
上記以外にも、個別の取引条件やその他の要因が価格に影響を与えることがあります。
- 売主の売却希望時期(売り急ぎかどうか)
- 売主が早期の売却を強く希望している場合(例:買い先行で次の住まいが決まっているなど)、相場よりも価格を下げてでも売却を優先することがあり、価格交渉の余地が大きくなることがあります。
- 買主の購入希望条件
- 買主のローン承認状況や、他の不動産の売却が条件となっているかどうかなど、買主側の事情も取引の成立や価格交渉に影響を与えることがあります。
- 引き渡し条件など
- 残置物の撤去、修繕箇所の負担、引き渡し時期など、売買契約における細かな条件も、価格交渉の材料となることがあります。
これらの価格影響要素を複合的に理解することで、単に表面的な価格だけでなく、なぜその価格になっているのか、その背景にある理由を読み取ることができるようになります。相場を調べる際には、これらの要素を考慮しながら、調査対象物件と比較物件を評価することが重要です。
不動産相場調査の注意点と、より正確な情報を得るためのコツ
相場調査を行う上で、いくつか注意しておきたい点と、より正確な情報を得るためのコツがあります。これらを押さえておくことで、誤った情報に惑わされず、より賢明な判断を下すことができます。
「売り出し価格」と「成約価格」は異なることを理解する
ステップ2でも触れましたが、不動産ポータルサイトなどに掲載されている「売り出し価格」は、あくまで売主が希望する価格であり、実際に買主と売主の間で合意に至った「成約価格」とは異なる場合がほとんどです。一般的に、成約価格は売り出し価格よりも低くなる傾向があります。
相場を把握する上で本当に重要なのは、市場で実際に取引が成立した価格、すなわち「成約価格」です。国土交通省の不動産取引価格情報検索や、不動産会社を通じて得られるREINSの成約事例データなどを活用し、成約価格の水準をしっかりと把握するようにしましょう。
売り出し価格だけを見て相場を判断してしまうと、実際よりも高い価格を相場だと誤解してしまう可能性があります。
情報の鮮度(いつの時点の情報か)と信頼性を常に確認する
不動産市場は常に変動しています。景気、金利、需給バランスといった市場環境や、周辺の開発状況などによって、相場は常に変化しています。そのため、相場情報を収集する際は、その情報が「いつの時点のものか」を必ず確認することが重要です。数年前の情報は、現在の相場とは大きく乖離している可能性があります。
また、インターネット上には様々な情報が溢れていますが、その全てが信頼できるとは限りません。情報の出典が明確か、公的な機関や信頼性の高い組織が提供している情報かなどを確認し、信頼できる情報源を選ぶようにしましょう。個人のブログや匿名掲示板など、信憑性の低い情報に惑わされないように注意が必要です。
一つの情報源に偏らず、複数のデータを組み合わせて総合的に判断する
相場調査においては、一つの情報源だけを鵜呑みにせず、複数の異なる情報源から得られるデータを組み合わせて総合的に判断することが重要です。
例えば、ポータルサイトで売り出し価格の傾向を掴み、国土交通省の取引価格情報で成約価格の水準を確認し、さらに不動産会社から周辺の成約事例データを提供してもらうといったように、様々な角度から情報を収集し、比較検討しましょう。それぞれの情報源にはメリット・デメリットや限界があるため、複数の情報を突き合わせることで、より客観的でバランスの取れた相場観を養うことができます。
不動産は個別性が高いため、類似物件でも条件が異なれば価格も変わることを認識する
一口に「類似物件」といっても、全く同じ条件の不動産は二つとありません。同じマンション内の同じ間取りの部屋でも、階数や方角、リフォームの有無、さらには売り急ぎの事情などによって価格は異なります。
相場を調べる際には、収集した情報にある物件が、調査対象の物件とどの程度似ているのか、そしてどのような点が異なるのかを意識することが重要です。築年数が近いか、広さはどのくらい違うか、リフォームはしているか、階数は同じか、といった点を比較し、その違いが価格にどの程度影響する可能性があるのかを考慮に入れながら判断する必要があります。完全に一致する事例がないからといって相場が分からないわけではなく、異なる点を考慮して価格を調整する視点が大切です。
最終的には、信頼できる不動産会社の担当者や不動産鑑定士などの専門家の意見を参考に判断する
ご自身で相場調査を行うことは非常に重要であり、取引を成功させるための第一歩となります。しかし、不動産の評価は専門的な知識や経験が必要な側面も多く、最終的な判断に迷ってしまう事が考えられます。
そのような場合は、信頼できる不動産会社の担当者や、不動産鑑定士などの専門家の意見を参考にすることが有効です。不動産会社は市場の最前線で活動しており、多くの取引事例や生きた情報を持っています。また、不動産鑑定士は専門家として、様々なデータや評価手法を用いて客観的な不動産の価値を評価します。
ご自身の調査結果と専門家の意見を照らし合わせることで、より精度の高い相場観を確立し、自信を持って取引に臨むことができるでしょう。複数の不動産会社に相談し、その対応や説明の分かりやすさ、信頼性などを比較して、安心して任せられるパートナーを見つけることも重要です。
まとめ
不動産の相場調査は、一見難しそうに感じるかもしれませんが、正しいステップと情報源を知れば、誰でも行うことができます。この記事で紹介した「調べ方(仕方)」を実践し、様々な情報を多角的に比較検討することで、より客観的な相場観を養うことができるでしょう。
相場を知ることは、不動産購入における高値掴みのリスクを減らし、適正な価格での購入を可能にします。また、不動産売却においては、適切な売り出し価格を設定し、希望する条件での売却を実現するための重要な基礎となります。さらに、不動産会社との交渉を有利に進めるための武器となり、具体的な資金計画やライフプランニングを現実的に行う上でも不可欠な情報です。
ご自身で相場を把握することは、情報格差による不利益を防ぎ、不動産取引で後悔しないための最も重要な準備の一つです。本記事で解説したステップ(情報の把握、オンラインツールの活用、公的データの参考、不動産会社への査定依頼、現地調査)を参考に、積極的に相場調査に取り組んでみてください。
不動産取引は、人生における大きなイベントの一つです。正しい「調べ方」をマスターし、自信を持って取引に臨み、納得のいく結果を手に入れてください。皆様の不動産取引が成功することを心から願っています。
参考文献
[1] 国土交通省 – 不動産取引価格情報検索 – https://www.mlit.go.jp/
[2] 公益財団法人不動産流通推進センター – REINS Market Information – https://system.reins.jp/
[3] 国土交通省 -令和6年都道府県地価調査 – https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_fr4_000001_00252.html
[4] 国税庁 – 財産評価基準書(路線価図・評価倍率表) – https://www.rosenka.nta.go.jp/
[5] SUUMO – https://suumo.jp/
[6] LIFULL HOME’S – https://www.homes.co.jp/