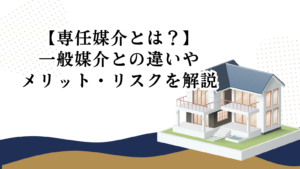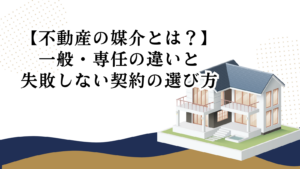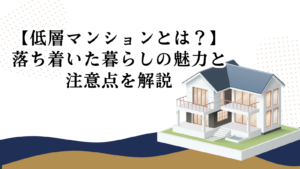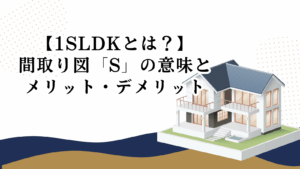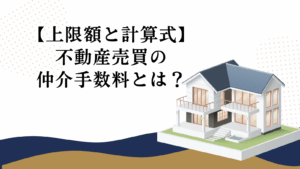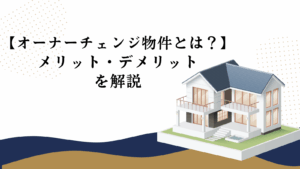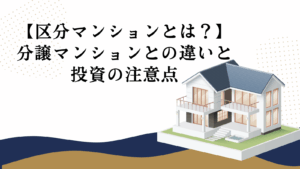親から子へ、あるいは祖父母から孫へ。大切な不動産を贈与したいと考えているけれど、
「贈与税がすごく高いって聞くから、損をするんじゃないか…」と不安を感じていませんか?
相続ではなく贈与で不動産を受け取る予定の方も、
どのような税金がかかるのか分からず戸惑うかもしれません。
不動産の贈与には、贈与税以外にも、不動産取得税や登録免許税など、
様々な税金や費用がかかることを知り、総額でいくらになるのか不安を感じることもあるでしょう。
「特例」があるらしいけれど、それが具体的にどのようなもので、
自分たちが適用できるのか分からない、という方もいるかもしれません。
この記事では、不動産の贈与にかかる税金の種類と計算方法、
そして具体的な税金対策や利用できる「特例」について分かりやすく解説します。
贈与か相続か、あるいは売買かなど、複数の選択肢がある中で、
どの方法が最も税金面で有利になるのかの判断基準まで、不動産の贈与に関する基礎知識を網羅的にお届けします。
これを読めば、不動産贈与にかかる税金の種類と仕組み、
利用できる特例について基本的な知識を理解し、漠然とした不安が解消されるでしょう。
不動産贈与、こんな税金の不安ありませんか?
不動産の贈与は、大きな資産が動く重要な手続きです。
税金に関するこんな疑問や不安を抱える方もいるのではないでしょうか?
- 不動産の贈与を検討しているものの、「贈与税がとても高い」という漠然としたイメージがあり、実行に踏み切れない。
- 贈与税以外にも、不動産登記費用や不動産取得税など、様々な税金や費用がかかることを知り、総額でいくらになるのか不安を感じている。
- 贈与税には「特例」があるらしいが、それが具体的にどのようなもので、自分たちが適用できるのか分からない。
- 親族間での贈与であり、後々の金銭トラブルや税金に関する指摘を避けたいと考えている。
- 不動産贈与に関する情報が複雑で、何が自分たちに必要な情報なのか、どう判断すれば良いのか迷っている。
- 贈与か相続か、あるいは売買が良いのかなど、複数の選択肢がある中で、どの方法が最も税金面で有利なのか比較検討したい。
- 一度贈与してしまうと元に戻せないため、手続きを進める前に徹底的に情報を収集し、後悔のない選択をしたい。
これらの不安を解消し、あなたが自信を持って不動産の贈与について判断できるよう、
この記事で深掘りしていきます。
不動産贈与にかかる税金の種類と計算方法
不動産の贈与を行う際には、いくつかの税金が発生します。
贈与税
- 贈与税とは
人から不動産やお金などの財産を贈与によって受け取った際にかかる税金です。
不動産の贈与の場合、不動産の評価額に対して税金がかかります。 - 基礎控除
1年間(1月1日~12月31日)に贈与された財産の合計額が110万円以下であれば、
贈与税はかかりません。これは「暦年贈与」と呼ばれ、最も基本的な贈与税対策です。
夫婦や親子など、贈与者と受贈者が複数いても受贈者一人あたり年間110万円までが非課税です。 - 計算方法
(1年間に受け取った財産の合計額 - 110万円の基礎控除額)× 贈与税率 - 控除額。
贈与税率は、贈与された財産の額や、贈与者と受贈者の関係(特例贈与と一般贈与)によって異なります。
不動産取得税
- 不動産取得税とは
土地や建物を購入したり、贈与によって取得したりした際にかかる税金です。
不動産の評価額に対して、一定の税率をかけて計算されます。 - 注意点
軽減措置が適用される場合もあります。
登録免許税
- 登録免許税とは
不動産の名義変更(所有権移転登記)を行う際にかかる税金です。
不動産の評価額や、登記の種類によって税率が異なります。 - 計算方法
固定資産評価額 × 税率。贈与による所有権移転登記の場合の税率は、
原則として20/1000(2%)です。
その他諸費用
司法書士への報酬(登記手続きの代行費用)や、不動産の評価額を証明するための
固定資産評価証明書の発行手数料などがかかります。
これらの諸費用も贈与の総額に含めて考慮しましょう。
不動産贈与の具体的な特例と活用法
贈与税は高いというイメージがありますが、
不動産の贈与には、税金を大きく軽減できる特別な制度(特例)がいくつかあります。
これらを活用することが、贈与の鍵です。
夫婦間の居住用不動産の贈与の特例(おしどり贈与)
- 概要
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、
居住用の不動産(またはその購入資金)を贈与した場合に利用できる特例です。 - 非課税限度額
基礎控除110万円とは別に、最高2,000万円までが非課税になります。 - メリット
合計で2,110万円まで非課税で不動産を贈与できるため、贈与税を大幅に抑えることができます。
配偶者への贈与を検討している場合に非常に有効です。 - 適用条件
婚姻期間20年以上、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその不動産に居住し、
その後も居住し続ける見込みであることなど。
住宅取得等資金の贈与の特例
- 概要
直系尊属(親や祖父母など)から子や孫へ、住宅の購入や新築、
増改築のための資金を贈与する際に利用できる特例です。 - 非課税限度額
省エネ等住宅であれば1,000万円、それ以外の住宅であれば500万円までが非課税になります
(時期によって変動する場合があります)。 - メリット
若い世代が不動産を購入する際の資金援助として、贈与税の負担を軽減できます。 - 適用条件
贈与を受ける人が18歳以上、合計所得金額が2,000万円以下(変動する場合あり)であること、
贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を購入・新築することなど。
相続時精算課税制度
- 概要
親や祖父母から贈与を受けたお金や不動産について、
贈与時には2,500万円まで贈与税がかからず(特別控除額)、
贈与者が亡くなった時に相続財産に加算して相続税を計算する制度です。 - メリット
贈与時の税金負担を軽減できるため、不動産を早めに子や孫に渡したい場合に有効です。 - デメリット
一度この制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与については暦年贈与(年間110万円の基礎控除)が利用できなくなります。また、贈与者が亡くなった際には、贈与時の評価額で相続財産に加算されるため、不動産の評価額が贈与後に上昇した場合は、相続税の負担が増える可能性があります。 - 注意点
他の特例との併用可否や、将来の相続税額への影響を慎重に検討する必要があります。
これらの特例をどう活用すれば良いかは、
個々の家族構成や資産状況、不動産の評価額によって大きく異なります。
贈与の具体的な手続きの流れと注意点
不動産の贈与手続きは、以下の流れで進みます。
- 贈与契約書の作成
贈与者と受贈者双方の意思確認のため、贈与する不動産の内容、
贈与の時期などを明記した贈与契約書を作成します。これは税金に関する証拠としても重要です。 - 登記書類の準備
不動産の権利証、印鑑証明書、住民票など、名義変更に必要な書類を準備します。 - 名義変更(所有権移転登記)
不動産が所在する管轄の法務局に、所有権移転登記を申請します。
この際に登録免許税を納めます。司法書士に依頼するのが一般的です。 - 不動産取得税の申告・納付
登記後に都道府県から不動産取得税の通知が来るので、期日までに納付します。 - 贈与税の申告・納付
贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、
管轄の税務署へ贈与税の申告と納税を行います。特例を適用する場合も申告が必要です。
注意点
- 金銭トラブルの回避
親族間でも、贈与する不動産の評価額や、税金・諸費用の負担について明確に取り決め、
書面に残しておくことが、後々のトラブルを避けるために重要です。 - 税務署からの指摘
「名義だけ贈与して、実際はお金のやり取りがあった」などと判断されないよう、
贈与契約書や税金の支払い記録などをきちんと残しておきましょう。
贈与か相続か売買か?最適な選択のための判断基準
不動産を次世代に引き継ぐ方法は、贈与の他にも相続や売買があります。
どの方法が最も税金面で有利になるかは、不動産の評価額、相続人の数、生前の贈与歴、
贈与を受ける側の資金力など、個別の状況によって異なります。
- 少額の不動産やお金
暦年贈与(年間110万円の基礎控除)を活用し、
複数年にわたって贈与していくのが有効な場合があります。 - 多額の不動産
特例(夫婦間の居住用不動産の贈与、住宅取得等資金の贈与など)や相続時精算課税制度の活用を検討します。 - 相続税対策
相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える資産がある場合、
生前贈与が有効な相続税対策となることがあります。 - 専門家への相談
不動産の税金は非常に複雑です。対策を考えるなら、税理士や司法書士といった専門家に
相談し、シミュレーションしてもらうのが最も確実です。
【まとめ】不動産贈与で賢く特例を活用しよう!
不動産の贈与は、大切な資産を次世代へ引き継ぐ有効な手段ですが、
税金に関する複雑な注意点が多く存在します。「贈与税が高い」というイメージから、
贈与をためらってしまう方もいるかもしれません。
しかし、贈与税には「夫婦間の居住用不動産の贈与の特例」や「住宅取得等資金の贈与の特例」、
そして「相続時精算課税制度」といった、税金を大きく軽減できる特例があります。
これらの特例をどう活用すれば良いのか、
自分のケースで適用可能かを見極めることが重要です。
この記事で解説した不動産贈与にかかる税金の種類と仕組み、そして具体的な特例の活用法を理解し、
漠然とした不安を解消しましょう。何から準備を始めれば良いか、
あるいはどの専門家に相談すべきか明確になったはずです。
不動産贈与に関するリスクを把握し、トラブルを未然に防ぐための注意点も踏まえ、
あなたにとって最適な方法を選択するための判断材料としてください。
賢く不動産を贈与し、大切な資産を次世代に引き継ぎましょう!
参考文献
・国税庁「贈与税のしくみ」: 贈与税のしくみ|国税庁
・国税庁「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの特例」: 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの特例|国税庁
・国税庁「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」: 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁